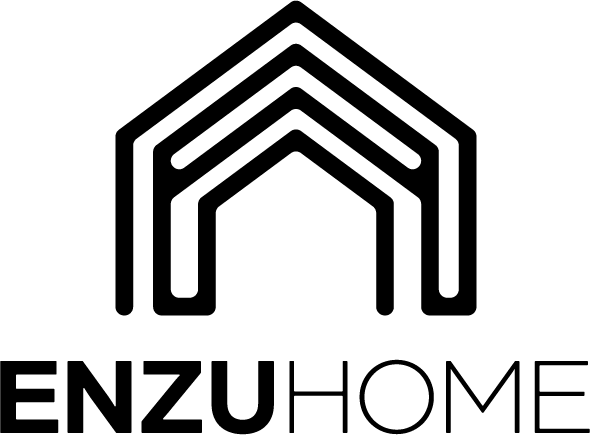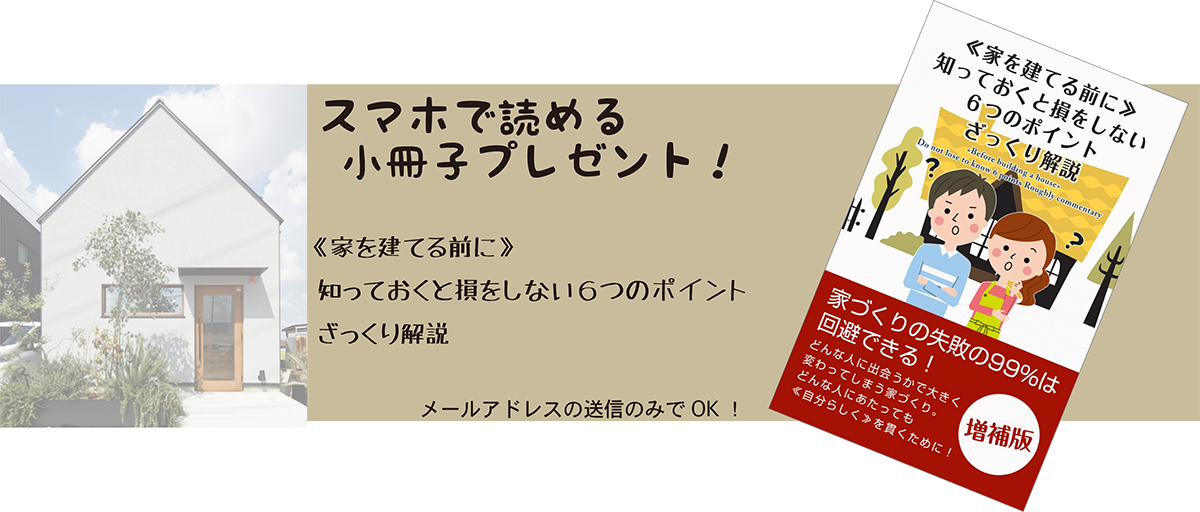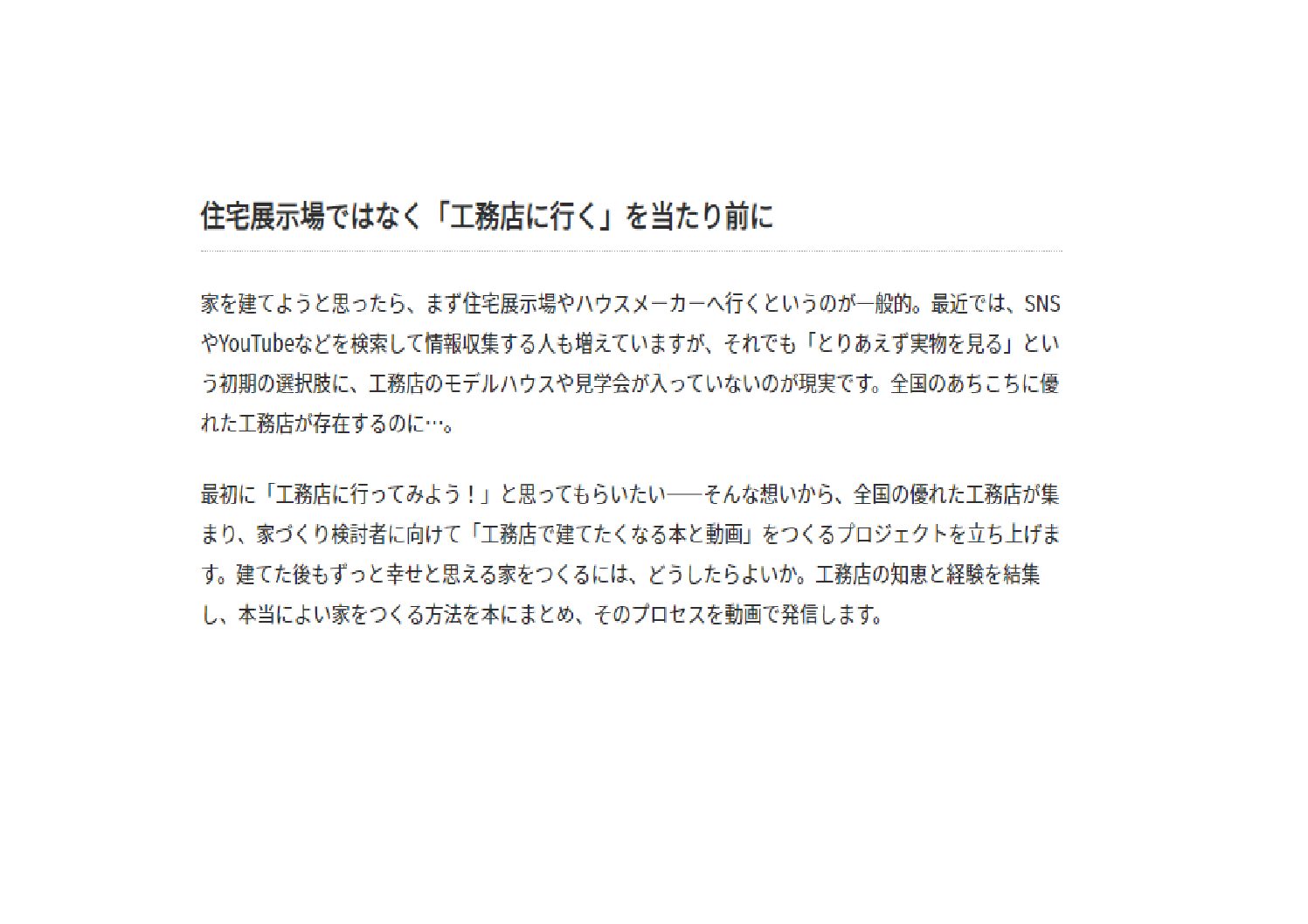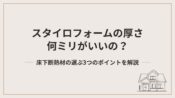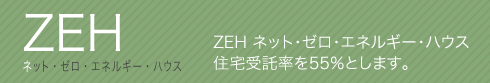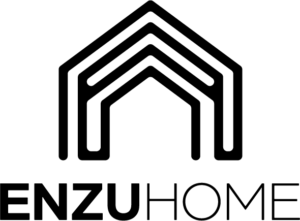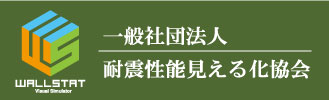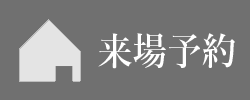耐震シェルターのデメリット5選や助成金についても解説
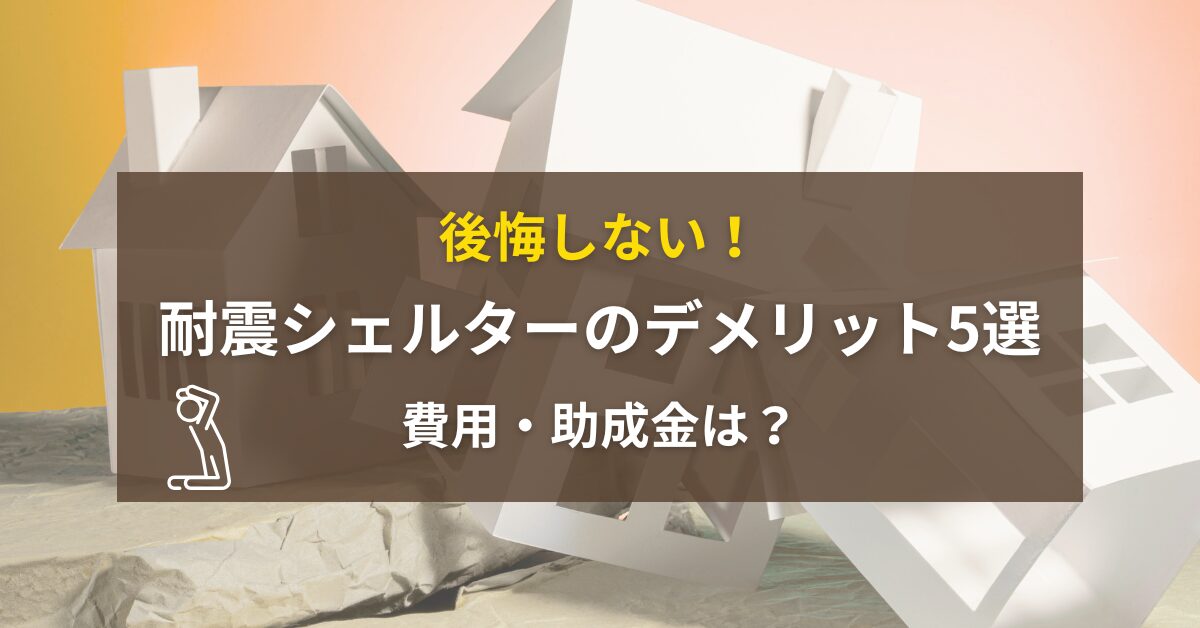
- 耐震シェルターって本当に効果があるの?
- どんな種類やメリット・デメリットがあるの?
- 設置費用や補助金制度も詳しく知りたい!
近年注目が集まっている「耐震シェルター」。
地震大国・日本において、家族の命を守るための備えとして検討される方が増えています。
でも、いざ導入を考えると「費用は?」「どのタイプがいい?」「補助金って使えるの?」といった疑問がたくさん出てきますよね。

そこで本記事では、住宅・防災の専門知識をもとに、耐震シェルターの種類からメリット・デメリット、費用相場、補助金制度まで、徹底的にわかりやすく解説します。
- 耐震シェルターのタイプと特徴
- 設置前に知っておきたいメリット・デメリット
- 補助金制度の仕組みと申請時の注意点
耐震シェルターは、費用を抑えて設置できるうえに、命を守る「最後の砦」とも言える存在です。
「家の耐震性に不安がある」
「でも大規模な耐震リフォームは難しい」
そんなあなたにこそ、ぜひ知っていただきたい内容を詰め込みました。
家族の安全を本気で考える方は、ぜひ最後までご覧ください。
関連記事:【知らないと後悔】「耐震等級3」と「耐震等級3相当」の違いやデメリット5つを解説!
耐震シェルターの悪い評判・口コミからわかるデメリット5つ
この記事のもくじ
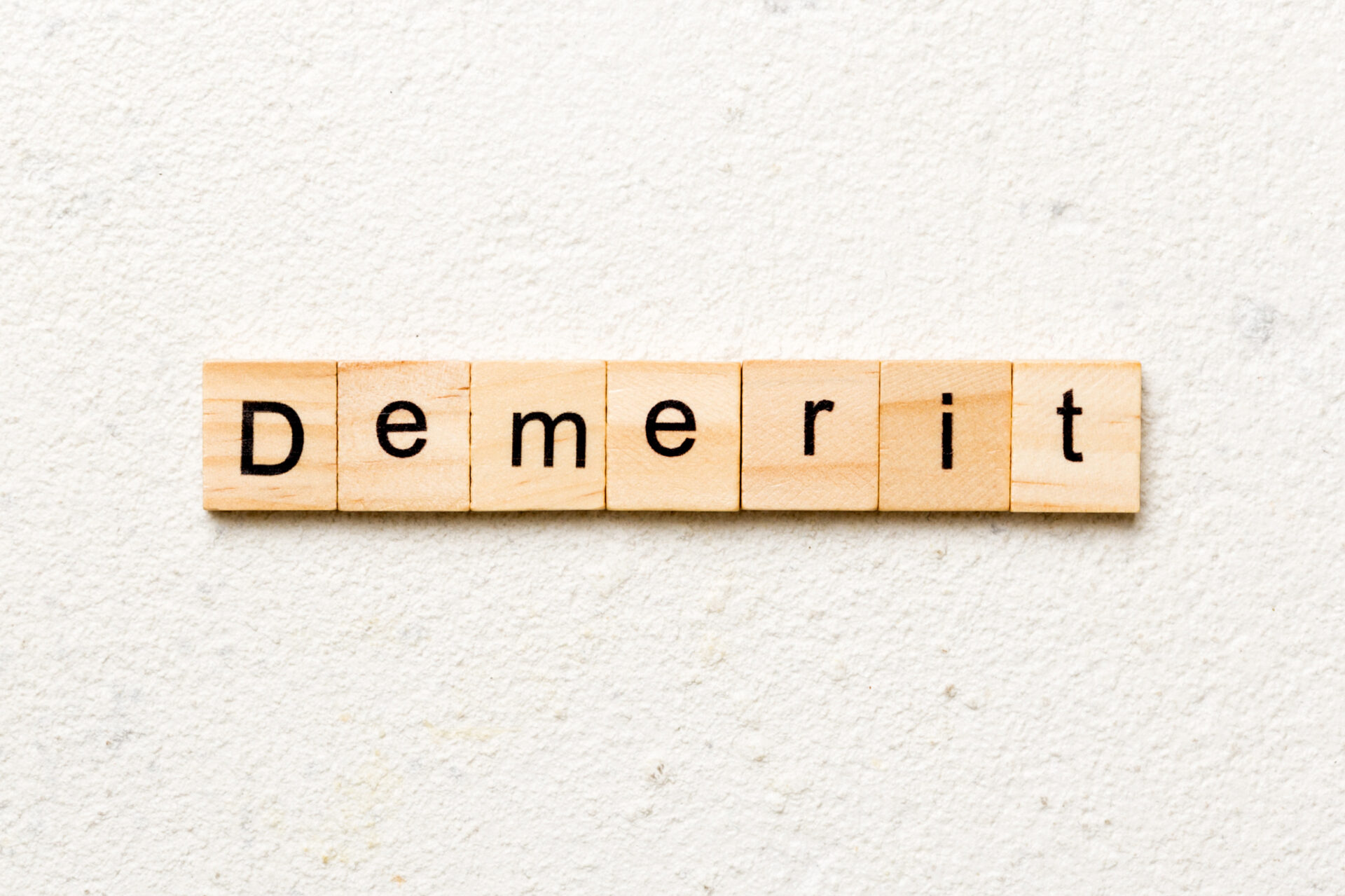
耐震シェルターは、住宅の中に設置することで家族の命を守る「避難空間」をつくれる便利な地震対策です。
実際に設置された方からは安心感に対する評価もありますが、一方で「こんなはずじゃなかった」と感じたという声も少なくありません。

ここでは、SNSや住宅情報サイトなどで見られるリアルな口コミをもとに、後悔しないために知っておきたい5つのデメリットをわかりやすく解説します。
デメリット①:設置した部屋以外の耐震性は変わらない
耐震シェルターの耐久性に関する公開実験で、屋根が落下した想定で砂袋を落下、シェルターの屋根を突き破る結果に。実験は「失敗」とありますが、改善点がわかったのであれば成功ではないですかね(方法が適切ではなかった場合は別)。
— 地盤災害ドクター横山芳春@住宅の災害リスクの専門家 (@jibansaigai) March 30, 2025
命を守る方策の1つとしては有効な策の1つでしょうか。 https://t.co/5xdSF4H8TE
市の測定結果
— 5/25関西コミティア F-57 ほかい (9月までインケツ) (@reiho2) November 17, 2024
恐ろしい家に住んどるんだけど
計測した人曰く
「明治維新前の建物は大概こんなもん」だそうで
それでも倒れてない建物が多いのは、この耐震測定法が現代建築前提だから
とは言っても安全て訳じゃないので、建物全部は予算的に無理でも、一部屋だけは耐震シェルターに改造工事してます pic.twitter.com/2Xuv7iNDGl
耐震シェルターは、家全体を補強するものではなく、あくまでもその場限りの「避難所」です。
例えば、寝室にシェルターを設置していたとしても、日中リビングにいたタイミングで大地震が起きてしまえば、シェルターの効果は発揮されません。

また、家全体の耐震性が高まるわけではないため、「安心なのはあくまで“その部屋だけ”」という点に不安を感じる方もいます。
「リビングにいたら使えない。夜寝るときしか安心できないのはちょっと…」
デメリット②:本体価格+床補強工事で費用がかさむこともある
今日は耐震シェルター設置のリフォーム工事現場
— TAKEZAWA Can (@eggsmile_koubou) April 10, 2025
Before pic.twitter.com/z8av7lNmVl
「低コストで設置できる」というのは耐震シェルターの魅力のひとつですが、実際には床の補強工事が必要になるケースが多く、予想以上に費用がかさむこともあります。
特に重量のある部屋型シェルターの場合は注意が必要で、既存の住宅構造によっては床を補強しなければ安全に設置できない場合があります。
以下は一般的な費用の目安です。
| 項目 | おおよその費用相場 |
|---|---|
| 家具型シェルター | 30万〜50万円 |
| 部屋型シェルター | 50万〜100万円 |
| 床の補強工事(必要な場合) | 10万〜20万円 |

設置場所の状況次第では、トータルで100万円以上かかる可能性もあります。
デメリット③:日当たりや風通しが悪くなる可能性がある
耐震シェルターや防災ベッドの導入にも自治体によって補助金が出ます。
— 地震防災ライフハックby家庭備災(お役立ち情報) (@kateibisaiinfo) June 7, 2024
家自体の耐震化は予算的に難しい場合、検討してみてはいかがでしょうか。
図表は静岡県の例ですが、お住いの自治体もぜひ調べてみて。 pic.twitter.com/5sAgMIXXbO
耐震性を高めるためには壁(耐力壁)や柱を多く取り入れる必要があり、その結果、窓が少なくなりやすくなります。
このため、特に部屋型のシェルターでは日当たりや風通しが悪くなるという声があがっています。
- 「窓が小さくて暗い…」
- 「風が通らなくて夏は蒸し暑い」

このように、快適性が損なわれるケースもあるため、設置場所や通風計画については事前にしっかり検討しておく必要があります。
デメリット④:商品によっては圧迫感・閉塞感が強い
【2/1】らくらくハウスにて最近施工した耐震シェルターを見学。多少圧迫感はあるけど木材の雰囲気はよい感じ。万が一周囲が倒壊してもこの部屋だけは残る頑丈さだとか。建物全体の補強は大変でもこれなら最小限の費用で耐震化できそう。少しでも空き家や住宅の地域的な活用を増やすにはよい方法かも。 pic.twitter.com/FBxMRMHGgA
— いちかわとおる (@icchii111) February 1, 2022
阪神淡路大震災のデータを仕事で調べたのですが、倒れてきた家具や落ちてきた天井に圧迫され続けたのが死因の『クラッシュ症候群』が散見されました。
— 鷹樹烏介@無法正義 許されざる警察 (@takagi_asuke) March 5, 2021
要介護のご老人で、年金生活なので大規模な耐震補強が出来ない古い家屋は、せめてシェルターベッドがいいのではないか? と思っています。 pic.twitter.com/Vnm35w31yq
ベッド型・テーブル型の家具シェルターはコンパクトに作られている反面、中に入ると圧迫感があると感じる方もいます。
特に高齢者や小さなお子さまがいる家庭では、狭さや暗さがストレスになる可能性も。

また、製品によっては構造上、外からの音や気配が遮断されやすいため、孤立感を覚えるという声もあります。
デメリット⑤:補助金対象外の自治体もある
予算の都合上、耐震シェルターは寝室だけなんで
— 5/25関西コミティア F-57 ほかい (9月までインケツ) (@reiho2) October 4, 2024
寝てるとき以外に大地震が来たら、迅速に安全な場所に移動せんといかん
耐震テーブルとか言うのがあって、揺れたときにその下に逃げ込むらしいので、それを購入するか?
「補助金が出る」と聞いて設置を検討していたのに、自分の自治体は対象外だったという声も多く見られます。
実際には、耐震シェルターに補助金が適用されるかどうかは自治体によって大きく異なります。
また、対象になるためには以下のような条件を満たす必要があります。
- 昭和56年(1981年)以前に建てられた住宅(旧耐震基準)であること
- 耐震診断の結果、「補強が必要」と判定されていること
- 対象製品が指定メーカーのものであること

補助金をあてにしていたのに、後から対象外とわかると大きな出費になるため、事前に自治体へ確認することが必須です。
耐震シェルターの良い評判・口コミからわかるメリット5つ

耐震シェルターは、地震時の命を守る「最後の砦」として注目を集めており、設置された方の満足度も高い傾向があります。

ここでは実際の評判や口コミをもとに、耐震シェルターが評価されている5つのメリットをわかりやすく解説します。
メリット①:耐震改修よりも費用が安く抑えられる
耐震シェルターという方法もあります。
— 菅 克己 (@Suga_Katsumi) February 6, 2025
地震対策で一番大切なのは、家を強くすること!死因の多くは、家屋倒壊と家財道具の下敷きです。
新耐震基準をクリアしても安全ではありません。耐震等級3の住宅を求めましょう。既に、多くの地震で耐震等級3の住宅被害が軽微であったデータがあります。… pic.twitter.com/VaTiYMmf9z
もっとも多く聞かれるのは、「コストを抑えて命を守れる」という声です。
耐震改修(家全体の耐震補強)は一般的に100万~200万円の費用がかかりますが、耐震シェルターであれば30万~100万円で済むケースがほとんどです。
| 対策内容 | 費用相場 |
|---|---|
| 耐震シェルター(家具型) | 約30万~50万円 |
| 耐震シェルター(部屋型) | 約50万~100万円 |
| 耐震改修工事 | 約100万~200万円 |

費用を抑えつつ、安心できる空間を確保できるのは、大きな魅力です。
メリット②:住みながら最短半日で設置できる
耐震シェルター設置のためにはまずは大規模断捨離をしないと。
— rikatsu (@serika100301) February 24, 2025
「工事が短期間で済む」という点も、多くの口コミで高評価を得ています。
特に家具型シェルターは、最短半日で設置完了するため、仮住まいや引っ越しの必要がありません。

部屋型であっても、1週間以内で工事が終わるケースが多く、住みながら設置できるため、生活への影響が最小限に抑えられます。
- 「仕事しながらでも施工してもらえて助かった」
- 「夜にはいつも通り家で過ごせた」
こうした声が寄せられています。
メリット③:賃貸住宅でも設置できる商品がある
建築知識がないと言ってること全て理解は出来ないと思うけど、タワマン云々の話じゃないよ。ミスリードされるな。センセーショナルに目を奪われるな。
— うだつ屋(仮) (@izayoyoi) May 10, 2023
このネタで最強なのは総合的に言えば賃貸と環境に応じた小規模な耐震シェルターを用意する事。
次点はホームレスね。
「持ち家じゃないから無理かと思ってたけど、賃貸でも設置できた!」という口コミも多く見られます。
最近では、組み立て式で床を傷つけずに設置できる製品も登場しており、マンションやアパートでも対応できるケースが増えてきました。
こんな方にもおすすめです。
- 賃貸住宅にお住まいの高齢者
- 単身世帯や子育て世帯
- 転勤が多いご家庭

退去時には取り外して引っ越し先でも再利用できる点も嬉しいポイントです。
メリット④:補助金で費用を大幅に削減できるケースもある
ここだけの話ですが『助成金・補助金一覧表』を今すぐに知って下さい。
— ひいらぎ (@hiiragi2280) May 16, 2024
買う前に必ずチェックしておいて下さい。最大"70万円"の給付金が出ます
気になる対象は↓
・耐震シェルター→40万円上限70万円
・止水板→工事費用の1/2上限50万円
・生ごみ処理機→購入金額3/4上限7万円… pic.twitter.com/js2TunT9j9
安全安心な兵庫づくりに向けて
— 兵庫県広報 (@hyogokoho) March 19, 2025
能登半島地震を踏まえた
ひょうご災害対策検討会の報告を
災害対策の充実・強化に活かします。
🚛トイレカーの導入
🏘️高齢世帯等への耐震シェルターの設置支援
📡災害拠点病院への低軌道衛星通信
(スターリンク)などの導入https://t.co/WVgB41NwAt pic.twitter.com/SiUfAjXQSp
多くの自治体が、耐震シェルターの設置に対する補助金制度を用意しています。
特に「旧耐震基準(1981年以前)」の住宅であれば、最大9割補助されるケースも。
【補助金活用例(東京都某区)】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象 | 旧耐震の木造住宅など |
| 補助内容 | 設置費用の9/10(最大45万円) |
| 条件 | 耐震診断結果で「補強が必要」など |

条件は自治体により異なりますが、申請すれば本体価格を実質0円で導入できるケースもあるため、必ず確認しておきましょう。
メリット⑤:引っ越し時に再利用できる

もうひとつの注目ポイントは、「耐震シェルターは繰り返し使える」ということです。
家全体の耐震改修とは違い、シェルターは持ち運び・再設置が可能なので、将来的に引っ越しや建て替えをする場合でも無駄になりません。
- 「将来実家を離れるつもりだったので、再利用できるのは大きい」
- 「子どもの家に引っ越すときにも持っていけた」

コストパフォーマンスを重視する方にとっても、大きなメリットといえるでしょう。
関連記事:木造住宅って耐震性は大丈夫?
耐震シェルターの2つの種類

耐震シェルターには主に2種類のタイプがあり、それぞれ用途や住まいの状況によって適した選択肢が異なります。

「どんな違いがあるのか」「自分に合うのはどちらか」を理解することで、より安全で効果的な導入が可能になります。
タイプ①:室内に独立した耐震空間を作る
耐震シェルターに寝室を引っ越して一週間
— 5/25関西コミティア F-57 ほかい (9月までインケツ) (@reiho2) January 26, 2025
窓の無い頑丈な箱の中
これが思いの外、落ち着く
家人など、ここに籠ってスイッチに没頭しとる pic.twitter.com/Tvm9S2XRQr
部屋型の耐震シェルターは、住宅の中に「もう一つの安全空間」を作るイメージです。
柱や梁などの構造材で囲いをつくり、一部屋まるごと高耐震構造に変えることで、倒壊時でも命を守れるスペースを確保できます。
主な特徴は以下のとおりです。
- 一室全体を強化できるため、避難時の自由度が高い
- 安定感があり、就寝時や家族全員の避難にも対応可能
- 製品によっては、設置後に空間としても使いやすい工夫あり
(例:木目調仕上げ、採光設計)
設置費用はやや高めですが、より安心感を求める方におすすめです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設置場所 | 主に1階のリビング・寝室など |
| 工期 | 約1週間前後 |
| 費用相場 | 約50万〜100万円 |
| 再利用の可否 | 再設置可能な製品もあり |

耐震性能が高く、家族全員が安心して使えるスペースを作りたい方に最適です。
タイプ②:ベッドやテーブルなどが避難スペースになる
夜間の地震発生時に避難所に向かうのは危険が大きい
— よしお (@goya73mint) January 29, 2025
自宅内に耐震スペースを用意してあれば安心だね
自治体の補助制度も広がり
耐震シェルターの開発や改良も日々進んでいるようだ
避難所問題の解消策の一つとして考えていいだろうね
家具型は、既存の家具のように使用できるタイプの耐震シェルターです。
普段はベッドやテーブルとして使えるのが特徴で、地震が発生した際にはそのまま避難スペースとなります。
主なメリットは以下のとおりです。
- 設置が非常に簡単で、最短半日で完了
- 工事不要で賃貸住宅にも導入可能
- コンパクトで目立ちにくく、圧迫感が少ない
価格も比較的リーズナブルで、手軽に命を守る手段を取り入れたい方に人気です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設置場所 | 寝室、子ども部屋、書斎など |
| 工期 | 半日〜1日 |
| 費用相場 | 約30万〜50万円 |
| 再利用の可否 | 再利用・移設可能 |

一人暮らしの方や高齢者世帯にもおすすめされることが多く、「最小限の手間で最大限の安心」を得られる選択肢です。
関連記事:耐震等級 大切にしたい命
耐震シェルター以外でおすすめの地震対策3つ

耐震シェルターは効果的な防災手段のひとつですが、それだけで万全とはいえません。
自宅全体の安全性を高めるには、複数の地震対策を組み合わせることが重要です。

ここでは、シェルター以外にも有効とされる代表的な地震対策を3つご紹介します。
地震対策①:家全体の耐震診断と補強工事
修正アップデートで伸び伸びになっていた耐震診断の報告書が来ました✨
— Whisky Student (@WhiskyRespect) January 27, 2025
設計や施工の業者さんが活用するデータなので弊社が持つ意味はあまり無さそうですが嬉しいです☺️
特に前々職の仲間の報告書が中に入っているのはとってもエモいです🥹#蒸溜所計画 pic.twitter.com/xDa8BrTHvN
耐震補強工事録/1軒の家で約9ヶ所の耐震補強工事🦾残り後2ヶ所 今日は押し入れ内を補強して強くしていきます🦾✨️🔨 #一般木造住宅耐震補強工事 pic.twitter.com/3pEsCMbaoG
— ゆうじ〈spin🌙off 〉 (@uo77557) April 22, 2025
まず最初に検討したいのが、家全体の耐震診断と補強工事です。
特に築20年以上の木造住宅にお住まいの方は、耐震基準が古いため危険性が高い可能性があります。
耐震診断では、以下のような項目をチェックします。
- 壁の配置バランス
- 屋根や基礎の状態
- 劣化や腐食の有無
診断後、必要に応じて「壁の補強」「金物の追加」「基礎補強」などを実施します。
補助金制度がある自治体も多く、補強工事費用の半額〜9割程度が助成される場合もあります。
| 内容 | 詳細例 |
|---|---|
| 耐震診断費用 | 0円〜数千円(助成ありの場合) |
| 補強工事の費用 | 50〜200万円 |
| 主なメリット | 家全体の耐震性を高められる |
| 補助制度の有無 | 多くの自治体で導入済み |

「我が家はどの程度地震に強いのか?」を知ることから始めるのが、最も安全な選択です。
地震対策②:制震ダンパーで揺れを吸収し、被害を最小化
高層ビルは免震だと思っていたんですが、制震というのもあるんですね。
— 家系拉麺 (@iekeiramen55) March 18, 2025
制震ダンパー自体がデザインになっていてカッコいい。
地震に対する建築物の技術は日本が一番だと思います。
勉強にもなりました。 pic.twitter.com/RVEuCrKSAS
制震ダンパーとは、地震の揺れを吸収・分散してくれる装置のことです。
建物の柱や壁に取り付けることで、構造体への負荷を大幅に軽減します。
特に繰り返し来る「余震」にも強く、耐震補強と併用することでより安全性が高まります。
制震ダンパーの特徴は以下のとおりです。
- 地震エネルギーを吸収し、揺れを最大70%軽減する製品もある
- 新築・リフォームのどちらにも対応
- 一部の自治体では補助金制度も利用可能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設置場所 | 壁内部・柱・梁の接合部など |
| 費用相場 | 約50万〜80万円 |
| 工事期間 | 約1日〜数日(リフォームの場合) |
| 対応可能建物 | 木造住宅中心、一部RCも対応 |

制震ダンパーは、住みながら設置できる点でも人気です。
壁を剥がさず施工できる製品もあるため、仮住まいの手間も不要です。
地震対策③:家具・家電の転倒防止対策を徹底する
大きい地震の余震かも💦備えなきゃ。
— えんど久子 (@Happyendo42) April 18, 2025
花瓶やガラス入りの額や掛け時計などは下に移動。開き戸の食器棚にストッパー。食器棚のコップの間にふきん。
家具の上の空間に高さに余裕がない空の段ボール箱を置き転倒防止。お風呂に水。枕元にクロックス。持ち出し荷物チェック。#防災減災#地震対策 pic.twitter.com/IOx3bJAuoD
建物の強度だけでなく、室内の安全性を高めることも重要です。
過去の大地震では、倒れた家具や落ちた家電によってケガをした事例が多く報告されています。
以下のようなグッズを活用して、日常的に備えをしておきましょう。
- L字金具で家具を壁に固定
- 家電や食器棚に滑り止めシートを設置
- 引き出しや扉のロックで中身の飛び出しを防止
- 照明や時計など吊り下げ物の落下防止
防災用品はホームセンターやネットショップでも購入可能です。

「今すぐできる地震対策」として、まずは転倒防止から始めてみるのも良い選択肢です。
耐震シェルターの助成金制度の特徴2つ

耐震シェルターの導入は費用がネックになりやすいですが、自治体の補助制度を活用すれば負担を大きく軽減できます。

多くの自治体では、「旧耐震基準」の住宅を対象に補助金を支給しており、最大で設置費用の90%がカバーされるケースもあります。
特徴①:補助制度の対象は旧耐震基準の住宅が中心
静岡ローカルニュース。旧耐震基準住宅の耐震化が80%を超えてから進まず、その6割が高齢者で問題に、って。資金もないし、残った年月も長くはないのだから当然。大切なのは家ではなく、命を守る事。高額な費用が掛かる家全体の耐震化ではなく、安価な室内シェルターの普及に切り替えるべきだろう。
— 日本国黄帝 (@nihon_koutei) September 28, 2016
大地震では
— 国鉄型好きな北陸の変なオッサン (@419SNKhketorngb) October 21, 2016
🔴古い(旧耐震基準)の建物
で
🔴1階に居る
🔴高齢者
が亡くなるケースが多い。ここ最近起きたのを見ると、この3つに該当するパターンはよく聞く。
寝室だけでもシェルターの普及・補助金がほしいとこ。
補助の対象となる住宅は、昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた「旧耐震基準」の建物が中心です。
また、自治体によっては以下のような条件を設定している場合があります。
- 耐震診断の結果、補強が必要と判断された住宅
- 指定された製品の中から選ぶ必要がある
- 所得制限や納税状況による制限がある

まずは、お住まいの市区町村でどのような制度があるのかを確認しましょう。
特徴②:補助金の有無や条件は自治体ごとに異なるため事前確認が必要
普段どの部屋にいる?
— シンシンD(技術士・一級建築士) (@Shinsuke_Suzu) January 5, 2024
どの部屋が一番安全?
地震が起きた時にどの部屋に逃げる?
ここ数日、母との対話で確認。
今日の新聞にも「住宅の一部を簡易的に補強し、逃げ込むスペースを確保するような耐震改修に対し、国などが支援を*」とあったが、耐震シェルター等に補助金を交付する自治体は多い。 pic.twitter.com/L30BcfqBeY
補助金の支給額や申請方法は自治体によって異なるため、導入を検討している方は必ず事前に情報収集を行うことが大切です。
以下に補助金制度の一例を紹介します。
| 自治体 | 補助金内容 | 主な条件例 |
|---|---|---|
| 新宿区 | 費用の9/10まで(上限45万円) | 昭和56年以前の木造住宅/耐震診断必要 |
| 荒川区 | 費用の9/10まで(上限50万円) | 予備診断で「補強必要」判定の住宅 |
| 今治市 | 耐震診断が自己負担3,000円から受けられる | 指定された建築士に依頼 |
申請時には、工事前に申請が必要なケースがほとんどです。
設置後に申請しても助成が受けられない場合があるので、必ず施工前に市区町村へ問い合わせてください。

また、「旧耐震」以外の住宅にも使える補助制度がある地域も一部存在します。
これも見落とさないようにしましょう。
耐震シェルターに関するよくある質問4選

耐震シェルターは近年注目されている地震対策ですが、導入を検討する上で気になる点も多いですよね。

ここでは、よくある質問とその答えをわかりやすく解説します。
質問①:防災ベッド・耐震シェルターは実際どうなの?
木質耐震シェルター70K 全国の自治体で展示 https://t.co/9O6Z39aMkz pic.twitter.com/KGXn2fyhYp
— PR TIMESライフスタイル (@PRTIMES_LIFE) November 8, 2024
防災ベッドや家具型耐震シェルターは、地震の際に上からの落下物や倒壊から身を守る避難空間として有効です。
特に次のようなケースで注目されています。
- 就寝中の地震対策をしたい人
- 高齢者や介護が必要な方がいるご家庭
- 賃貸住宅やマンションに住んでいて大がかりな工事ができない人

メリットとしては、設置のしやすさや費用の安さが挙げられますが、シェルター以外の部屋の安全性は変わらない点に注意が必要です。
質問②:耐震シェルター(安全ボックス)はどう?
耐震シェルター、一軒家の中に25万円で設置できるんですって。家が崩れても、その部屋だけは崩れないと。自治体の補助を使えば、自己負担なしで設置できることもあるって。これっていいんじゃない?
— ʕ ·ᴥ·ʔっ ♪♫♫♪ (@macomocom) March 2, 2011
「安全ボックス」とも呼ばれる耐震シェルターは、強固なフレームで作られた空間を室内に設置し、地震の際の「最後の砦」として機能します。
- 人命を守るシンプルかつ確実な構造
- 工期が短く、住みながらの設置も可能
- 製品によっては見た目もスマートで圧迫感が少ない

特に木造住宅に住んでいる方にとっては、耐震補強の代替策や追加対策として現実的な選択肢と言えるでしょう。
質問③:耐震シェルターは自作できる?
ボロアパートに住んでる全国の学生は、部屋の中に耐震シェルターを自作するべきかもしれない。
— yu (@Nc2012_700x) April 17, 2016
家が古すぎて耐震補強は諦めた口です。。
— Miyashion (@Miyashion_DIY) August 9, 2024
寝てるときの自作シェルターは有用だと感じた。。
「DIYで耐震シェルターを作れないか」と考える方もいますが、基本的にはおすすめできません。
理由は以下のとおりです。
- 十分な強度・耐荷重を確保するには専門知識が必要
- 耐震実験や品質試験がされていないため、安全性が不明
- 万が一のときに法的な保証が受けられない

命を守るための装置である以上、専門メーカーの製品や有資格者による施工を強く推奨します。
質問④:耐震シェルターの価格はどのくらい?
地震時に命を守る為に自宅の耐震化が一番の対策ですが
— カズエナガ (@1123kzkz) February 22, 2023
「耐震診断」をして見積もりを見たらキャ〜😱アルアル
一部だけでもできますよ☝
今回は低価格なシェルター製品を紹介させて頂きます。 pic.twitter.com/xYy0Otk0cN
耐震シェルターの価格は、タイプやサイズによって異なります。
以下はおおよその費用目安です。
| シェルターの種類 | 費用相場(税・施工費込み) | 特徴 |
|---|---|---|
| 家具型(ベッド/テーブル) | 30万〜50万円 | 設置が簡単。半日で施工可能 |
| 部屋型 | 50万〜100万円 | 部屋全体を保護。設置に1〜2日 |
| 特殊・オーダー型 | 100万円以上 | サイズや仕様により変動 |

また、自治体によっては40万円以上の補助金が出るケースもあり、自己負担を抑えられる可能性があります。
まとめ:耐震シェルターを取り入れて家族の命と安心を守ろう

- 万が一の地震に備えるための安全空間の確保
- 費用・工期・再利用性に優れた耐震シェルターの導入
- 自治体補助金や他の地震対策と併用した防災対策
いつ起きるかわからない大地震に備えるためには、「いざというとき、命を守れる空間があるかどうか」が非常に重要です。
耐震シェルターは、比較的安価かつ短期間で設置できる現実的な防災対策として注目を集めています。
特に以下のような方には、導入を検討する価値があります。
- 耐震補強は難しいが、最低限の安全対策を講じたい
- 家族の就寝中の安全を確保したい
- 高齢者や子どもがいるため、避難に時間をかけたくない
- 賃貸住宅などで大がかりな工事ができない
耐震シェルターは、部屋型・家具型など用途に応じた製品があり、自治体によっては補助金制度も利用できます。

また、「制震ダンパー」や「家具の転倒防止」など、他の地震対策と組み合わせることで、より安全性を高めることができます。
大切な家族と住まいを守るために、今できる地震対策のひとつとして、耐震シェルターの導入をぜひ前向きに検討してみてください。
関連記事:耐震について僕なりに考えたんです。