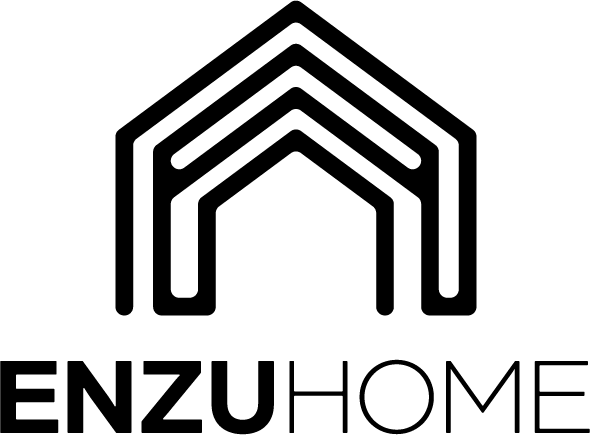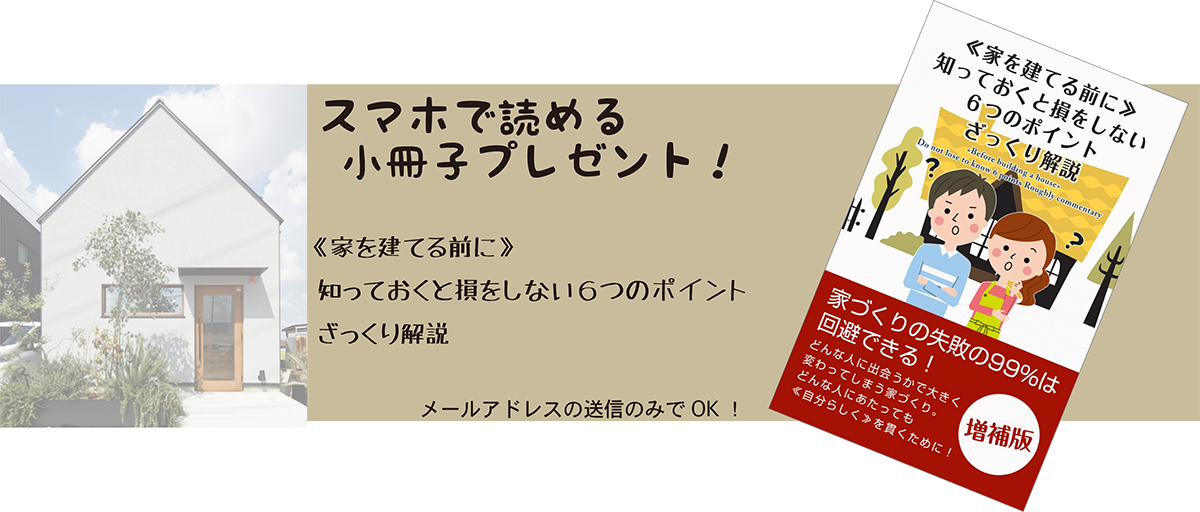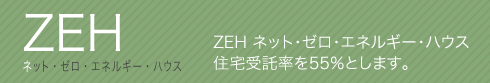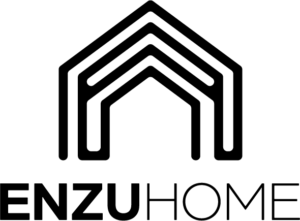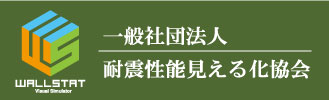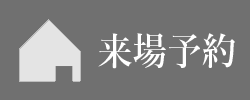新築の予算オーバーで後悔しないための5つの原因や対策を解説
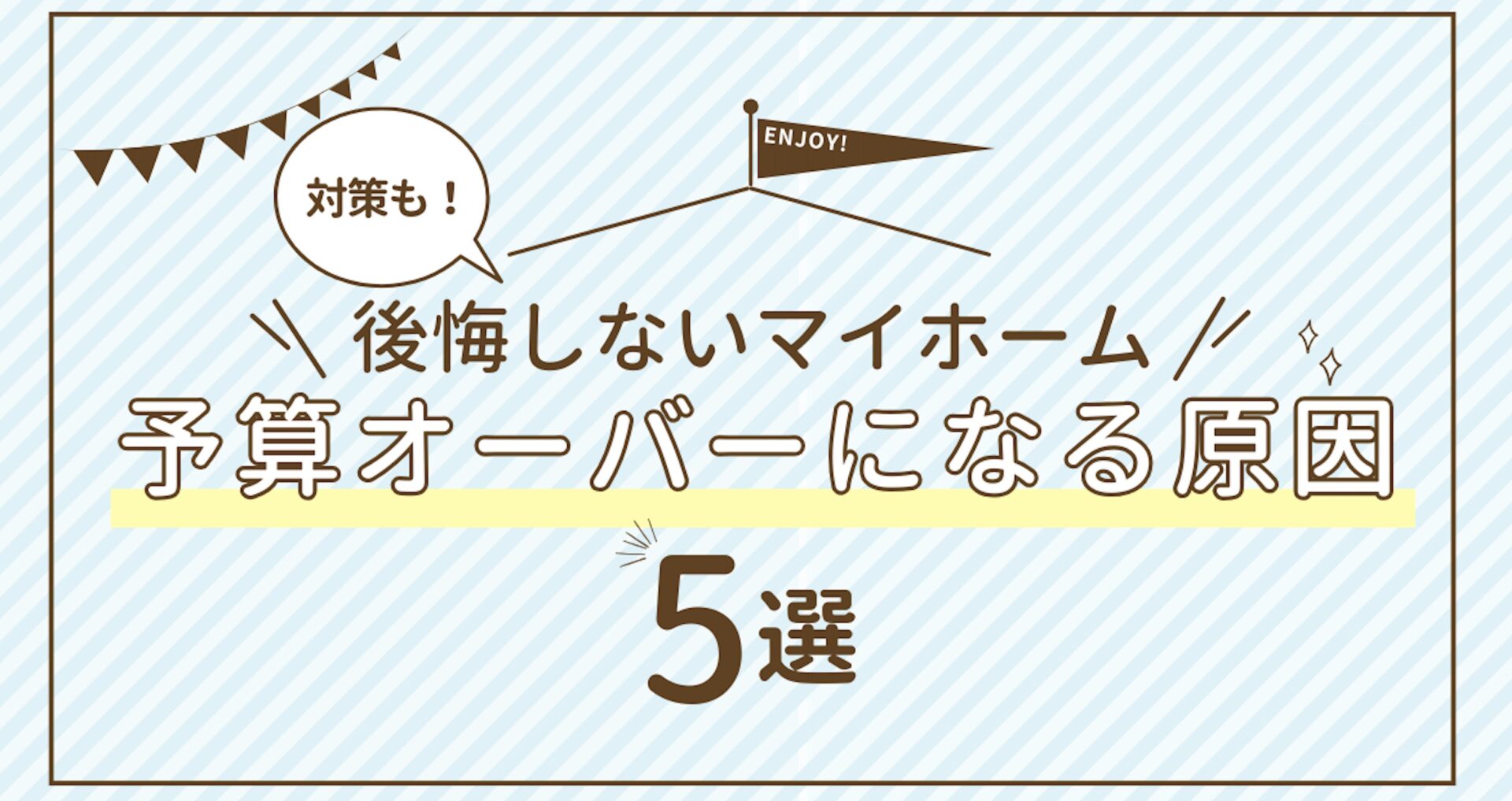
- 注文住宅で予算オーバーして払えないときの対処法が
知りたい - 新築住宅で予算オーバーしないためのコツを知りたい
- 削るべき費用と削ってはいけない費用を見極めたい
注文住宅を建てる際、予算オーバーして「払えない」と悩む方も多いですよね。

そんな不安を解消するために、住宅業界のプロが、予算オーバーしやすいポイントや具体的な対策を徹底解説します。
- 新築住宅で予算オーバーする原因
- 予算オーバーしないためのコツ
- 削るべき費用と削ってはいけない費用の判断基準
注文住宅を検討している方や、すでに予算オーバーに悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
新築住宅で予算オーバーする5つの原因
この記事のもくじ

注文住宅を建てる際に、予算オーバーが発生する原因はさまざまです。

特に、以下の5つのポイントが予算オーバーの主な原因として挙げられます。
しっかりと把握して、計画段階から注意を払うことが大切です。
原因①:建築費用以外の諸費用を考慮していなかった
三郷遠征だん。地元の不動産屋の社長によると、TX三郷中央徒歩圏が人気だが新築建売で4,000万オーバー。予算が合わない場合はさらに北上。新三郷や三郷など武蔵野線沿線は、乗換ネックで移住組が少ない。地元の人の住み替え需要が多めとのこと。三郷中央と三郷は一千万違う。都心直通いと強し。 pic.twitter.com/iUAxWDRKOu
— すんで埼玉 (@sunde_saitama) November 16, 2020
建物本体の工事費用だけで予算を考えてしまうと、その他の費用が見落とされがちです。
以下のような諸費用が発生するため、あらかじめ把握しておく必要があります。
| 費用項目 | 内容 |
|---|---|
| 付帯工事費 | 給排水工事や電気工事、外構工事など |
| 申請手続き費用 | 建築確認申請や登記費用 |
| 税金・保険料 | 不動産取得税、登録免許税、火災保険料など |
| 引っ越し費用 | 新居への引っ越しやインテリア購入費 |

これらの費用が建築費用の20~30%を占めることもあるため、資金計画の段階でしっかり計算しておきましょう。
原因②:契約後の仕様変更やオプション追加が多かった
新築住宅。
— 常盤聡【Jリーガー初不動産社長】 (@tokiwasatoshi) December 17, 2019
完成間近。
憧れの注文住宅というのは、
なんでもオーダーできる分
予算をオーバーしてしまいがち。
最初からその値段になるなら教えて欲しかった。
こんな声がザラにある。
一生に一度の買物にカラクリはいらない。#お客様第一#寿建設#注文住宅#不動産売買#買取 pic.twitter.com/H0mtxruPKr
契約時には予算内に収まっていたとしても、打ち合わせが進む中で仕様変更やオプション追加を重ねると費用が膨らみます。
例えば、以下のようなケースがあります。
- キッチンや浴室のグレードをアップした
- 外壁材を耐久性の高いものに変更した
- エアコンや照明を追加した

特に、見積もり後に「やっぱりこっちにしたい」と変更を加えると、追加費用がかかりやすいです。
契約前に仕様をしっかり確認し、優先順位を決めておくことが大切です。
原因③:土地購入に予算をかけすぎた
基礎工事スタート
— セニョ (@senyooyakata) March 2, 2022
もはや、新築しなければ良かった
と思うぐらいの予算オーバー⁉️
土地の利益を食い散らかす
土地が安く仕入れれてなかったら
死んでました😇
知識、段取不足もあって
工期と気持ちの余裕がありゃしません
😭
やるしかねぇー pic.twitter.com/XHcqVjxXo9
土地代に予算をかけすぎて、建物に充てる費用が足りなくなるケースも多く見られます。
特に、以下のようなポイントに注意しましょう。
- 駅近や人気エリアの土地は割高になりやすい
- 整地や地盤改良が必要な土地は追加費用がかかる
- インフラ整備が不十分な土地は、配管工事などのコストが発生する

土地探しの際には、地盤や周辺環境も考慮して、総合的に判断することが重要です。
原因④:建築中の不測の事態による追加工事が発生した
新築の総費用がやっと見えてきた。設備や内装、電気工事の追加等でかなりアップし(これでもかなり妥協できる部分を削ったのだが)、元々の予算を若干オーバー。外構工事も一体どこまでやるか…。
— キイロ (@Kiiroi_otoko) August 23, 2018
建築中に予期せぬトラブルが発生し、追加工事が必要になる場合もあります。
例えば、以下のような事態が考えられます。
- 地盤が軟弱で、地盤改良工事が必要になった
- 設計段階で気づかなかった配管トラブルが発生した
- 工事中の天候不良で作業が遅れた

これらの問題を避けるためには、事前調査をしっかりと行い、不測の事態に備えた「予備費」を確保しておくことが大切です。
原因⑤:住宅会社とのコミュニケーション不足

住宅会社との情報共有が不足していると、必要な工事が見積もりに含まれていないことがあります。
特に次の点には注意が必要です。
- 見積書の内容を詳細に確認しなかった
- 打ち合わせ記録を残していなかった
- 工事範囲を曖昧にしたまま契約してしまった
契約前に工事内容を具体的に確認し、不明点があれば必ず担当者に確認しておきましょう。

また、打ち合わせ記録を保存しておくことで、トラブルを未然に防げます。
「予算オーバーで払えない」とならないための対策5つ
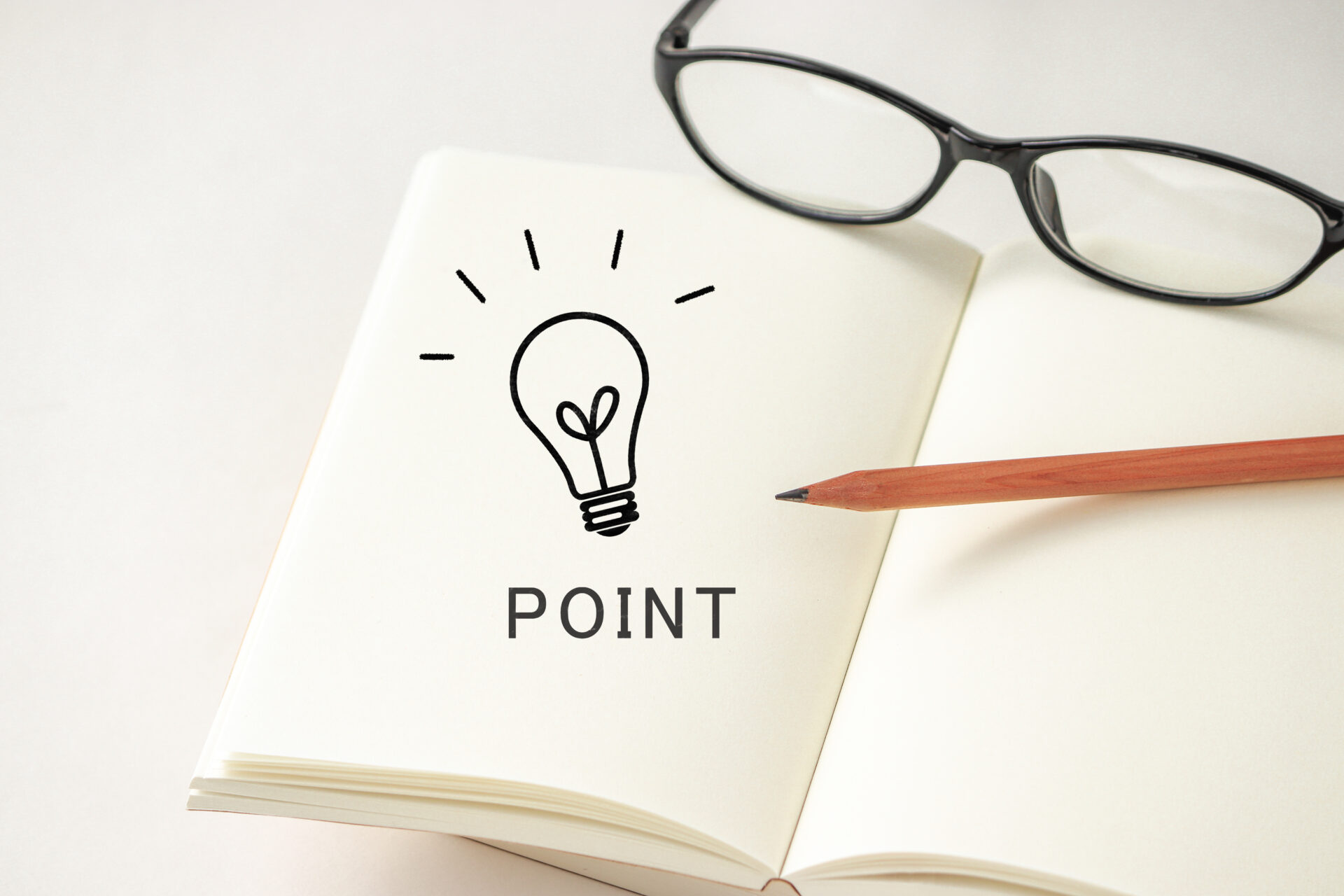
新築住宅を建てる際、予算オーバーが発生すると「払えない」と悩むケースが少なくありません。

そこで、予算オーバーを防ぎ、安心して家づくりを進めるための5つの対策を紹介します。
対策①:詳細な資金計画を立てる
最近任意売却の買取依頼しかこない。
— ゆう@不動産(3)🕊 (@you06955488) February 20, 2024
バブル最高値を突破しようとしてる日本でいったい何故⁉️
何が起こってるの。
築数年で払えなくなるって、最初から資金計画に無理があったと思うんだけど。
皆さんは正直工務店で新築してくださいね。
家づくりを成功させるためには、建物本体の費用だけでなく、関連する諸費用まで含めた資金計画が重要です。
以下のポイントを押さえながら計画を立てましょう。
| 計画に含める項目 | 内容 |
|---|---|
| 建築費用 | 建物本体費用、設計費用、設備工事費など |
| 土地取得費用 | 土地代、仲介手数料、登記費用 |
| 付帯工事費用 | 地盤改良工事、外構工事、給排水工事など |
| 諸費用 | 火災保険料、不動産取得税、引っ越し費用など |

これらをもれなく見積もり、余裕を持たせた計画を立てることで、「払えない」リスクを減らせます。
注文住宅の新築にかかる費用を詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
対策②:住宅ローンの返済可能額を把握する

住宅ローンを組む際、借入限度額だけでなく、月々の返済額が家計に与える影響も考慮しましょう。
一般的には、以下の基準を目安にすると無理のない返済が可能です。
- 返済負担率:年収の20~25%
- 毎月の返済額:月収の25~30%以内
例えば、年収500万円の場合、返済負担率を20%とすると年間返済額は100万円、月々約8.3万円です。

この範囲を超えると生活費に影響が出るため、無理のない計画を心がけましょう。
対策③:予備費を確保しておく

家づくりでは予期しない費用が発生することが多々あります。
以下のケースに備えて、予備費を確保しておきましょう。
- 建築中のトラブル:地盤改良や配管工事の追加費用
- オプションの追加:デザインや設備の変更に伴う増額
- 生活関連費用:新居への引っ越し費や家具購入費
一般的には、全体予算の5~10%程度を予備費として確保するのが理想です。

「もしもの備え」があることで、急な支出にも対応できます。
対策④:早めに「払えない」リスクを見極める

家づくりの計画段階で「このままだと払えない」と感じたら、早めに対策を講じましょう。
以下の対応が有効です。
- 住宅会社へ相談:プランや仕様を見直す
- 住宅ローンの変更:返済期間を長くして月々の負担を軽減
- 支出の見直し:不要なオプションや設備をカット

予算オーバーに気づいた時点で速やかに対応すれば、後から困るリスクを減らせます。
対策⑤:柔軟に相談できる住宅会社を選ぶ

住宅会社との信頼関係が薄いと、トラブルが起きた際に適切なアドバイスを受けられないことがあります。
選ぶ際は、以下のポイントを重視しましょう。
- 見積もりが明確である:項目ごとに費用が記載されている
- アフターフォローが充実している:完成後もサポートがある
- 資金計画の提案力が高い:無理のない支払いプランを提案できる

口コミや実績を確認し、予算相談に応じてくれる会社を選ぶと安心です。
エンズホームは予算に応じて提案いたしますので、少しでも興味がある方はぜひお気軽にモデルハウスの見学においでください。
注文住宅の予算の立て方4つのステップ

注文住宅を建てる際には、予算の立て方が非常に重要です。
しっかりと計画を立てることで、予算オーバーや「払えない」といったリスクを防げます。

ここでは、注文住宅の予算を立てるための4つのステップを解説します。
ステップ①:自己資金と借入可能額を確認する

まずは、自己資金と借入可能額をしっかり確認しましょう。
注文住宅を建てる際の資金は、自己資金と住宅ローンが基本です。
以下の点を押さえておきましょう。
- 自己資金:貯金や親からの援助、売却益など
- 借入可能額:金融機関の事前審査で確認できる金額
- 予備費:予算全体の10%程度を確保
例えば、貯金が500万円あり、借入可能額が3000万円の場合、自己資金と合わせた3500万円が基本予算となります。

ただし、無理なく返済できるかを考慮し、全額借入するのは避けましょう。
ステップ②:月々の返済額をシミュレーションする
お金がないけど家族でとにかく新築に住みたい!都内まで通勤が必要…なら自分だったらこのあたりを狙いますかね。住宅ローン返済額4万台… pic.twitter.com/q0K2M1pBRP
— ぷーたろう (@taro0829) February 22, 2024
住宅ローンを借りる際には、月々の返済額が無理のない範囲かを確認することが大切です。
以下の基準を目安にしましょう。
- 返済負担率:年収の20~25%以内が理想
- 月々の返済額:月収の25~30%以内に抑える
例えば、年収500万円の場合、返済負担率を20%とすると年間返済額は100万円、月々約8.3万円が適正範囲です。

住宅ローンの返済額シミュレーションを活用し、金利や返済期間を変えて複数のパターンを比較しておくと安心です。
ステップ③:土地購入費と建築費をバランスよく配分する

注文住宅では、土地購入費と建築費をバランスよく配分することが重要です。
以下の割合を目安にしましょう。
| 項目 | 配分割合 | 内容 |
|---|---|---|
| 土地購入費 | 30~40% | 土地代、仲介手数料、登記費用など |
| 建築費 | 50~60% | 建物本体費用、工事費、設計費など |
| 諸費用・予備費 | 10~20% | 登記、引越し、保険、その他付帯工事など |
例えば、総予算3500万円の場合、土地購入費は1000~1400万円、建築費は1750~2100万円、諸費用として350~700万円が目安です。

土地選びの際は、周辺環境や利便性だけでなく、建築費に影響を与える地盤の状態や付帯工事の有無も考慮しましょう。
ステップ④:入居後の維持費も考慮する

住宅を建てた後にも、維持費がかかります。
これを見落としてしまうと、入居後に家計が圧迫される原因となります。
考慮すべき維持費は以下のようなものです。
- 固定資産税:土地や建物にかかる税金
- 火災・地震保険料:保険料や更新費用
- メンテナンス費用:屋根や外壁の塗装、設備の修繕
- 光熱費:断熱性や設備仕様により変動
例えば、年間の固定資産税が15万円、保険料が10万円かかる場合、月々約2万円を維持費として見込む必要があります。

入居後のランニングコストを考慮した資金計画を立てておくと、安心して暮らせます。
新築の注文住宅のコストダウン4つの事例

注文住宅はこだわりが詰まった家づくりができる反面、予算が膨らみやすいという課題があります。
ここでは、コストダウンにつながる4つの具体例を紹介します。

賢く工夫することで、理想の住まいをお得に実現しましょう。
事例①:建物の形状をシンプルにする
レンタル倉庫新築
— おさむ@経営者になる元メカニック (@car_soliloquy) August 16, 2021
これで9万円✨
予算オーバーだけどかなりイイ pic.twitter.com/BBGyyzJ9xA
建物の形状が複雑になると、材料費や施工費が増加します。

特に以下の形状はコストが高くなりやすいです。
| 形状の種類 | コストが高くなる理由 |
|---|---|
| 凹凸の多い外観 | 外壁面積が増え、材料費がかさむ |
| L字型やコの字型 | 耐震補強が必要になり、構造が複雑化 |
| 多面体屋根(寄棟など) | 屋根材や工数が増加し、施工費が高騰 |
総二階建てにすることで、1階と2階の壁が揃うため構造がシンプルになり、耐震性も高まります。
屋根形状を「切妻」や「片流れ」にすることで、材料費と施工費を削減できます。
事例②:延床面積を減らす

延床面積が広がると、その分建築費が増加します。

居住スペースを見直して、無駄な空間を省きましょう。
- 廊下を短くする:リビング直結型の間取りにする
- 収納を一カ所にまとめる:ウォークインクローゼットを活用
- ホールやバルコニーを最小限に:空間をコンパクトに
【コスト比較:リビングの広さ】
| リビングの広さ | コスト | 特徴 |
|---|---|---|
| 20畳 | 約200万円 | 開放感がありゆったり |
| 18畳 | 約180万円 | 必要十分な広さ |
| 16畳 | 約160万円 | 家族4人なら十分 |
広すぎるリビングは冷暖房効率が悪く、電気代もかかります。
使いやすさを重視しながら、無駄を減らすことが大切です。
事例③:標準仕様やグレードを見直す
大○健託の営業に粘られて、値引きもして貰い若干予算よりオーバーだったものの、お試しということもあり、請負契約し無事着工。
— 天空大家🪐@天空不動産 (@tenku_ooya) July 9, 2021
大手ハウスメーカーでRC新築は初めてなので、どんな感じで進むのか! pic.twitter.com/2vBTaHJaYH
注文住宅では、キッチンやバスルーム、床材などのグレードが総額に大きく影響します。

標準仕様に変更したり、グレードを下げることでコストを抑えましょう。
【設備のグレード見直し例】
| 設備 | 高グレード | 標準仕様 | 節約効果 |
|---|---|---|---|
| キッチン | 大理石カウンター | 人工大理石 | 約20万円削減 |
| バスルーム | 高機能浴室乾燥機 | 換気扇のみ | 約15万円削減 |
| 床材 | 無垢材 | 複合フローリング | 約30万円削減 |
キッチンや床材は後からリフォームが可能なため、新築時は標準仕様にしておき、将来必要に応じて変更すると良いでしょう。
事例④:外構工事を後回しにする
今日で4月も最終日
— mimimi︎︎︎@2y+0m(38w1d) (@mimihana__) April 29, 2023
今月は夫の繁忙期も落ち着き(?)
家族3人、2泊3日でおでかけできたのは
良き思い出になった👨👩👦
それと新築してから後回しになっていた一部外構工事の話も少しずつ進められそう😇
予定日10日後🤍新車お迎えして席用意して待ってるよ👶元気に産まれてきてね
新居で暮らし始めてもう5ヶ月経つし、いい加減表札を買わないと💦番地入りの表札がいいなあと思って色々探してる👀後回しにすると絶対にしなくなると思って外構工事は無理してでも新築と同時にした。結果正解。後回しにしてたら表札買うのですら5か月後😂
— Rica (@Rica22460284) January 12, 2024
外構工事は、駐車場の舗装や庭の整備、フェンスの設置などに多くの費用がかかります。

初期費用を抑えるために、入居後に少しずつ整備する方法を検討しましょう。
【外構工事の優先順位】
| 項目 | 優先度 | 初期対応 | 後回し対応 |
|---|---|---|---|
| 駐車場舗装 | 高 | 砂利敷き | コンクリート舗装 |
| フェンス設置 | 中 | 必要部分のみ | 後からDIY |
| 庭の植栽 | 低 | シンボルツリーのみ | 庭づくりは後日 |
フェンスやガーデニングなどはDIYで行うと、プロに依頼するよりコストを大幅に削減できます。
住みながら必要性を見極めてから整備することで、無駄が減ります。
注文住宅の予算オーバーで削るべき3つの箇所

注文住宅で予算オーバーしてしまった場合、すべての費用を削るのは現実的ではありません。

そこで、生活に支障が出にくく、削減しても大きな問題になりにくい3つの箇所を紹介します。
箇所①:内装や設備のグレード

高級仕様の内装や設備は、費用がかさみやすいポイントです。

例えば、システムキッチンやバスルームをハイグレード仕様にすると、数十万円単位でコストが上がります。
まずは内装や設備のグレードを見直し、標準仕様に変更できないか検討しましょう。
- 【キッチン】ハイグレードIH → 標準IH
- 【バスルーム】自動乾燥機付き → 手動乾燥
- 【壁紙】輸入クロス → 国産クロス
内装や設備は、引き渡し後にリフォームしやすいため、初期費用を抑えたい場合は優先的に見直すと良いでしょう。
箇所②:部屋数や延べ床面積
設計施工やらせて頂いた新築物件の最終チェック。予算の兼ね合いもあって坪数を15坪に抑えた小さな平屋間もなく完成です🙋♂️
— まだらめ (@madarame_links) January 28, 2025
間仕切りをできる限り少なくして空間の有効活用、玄関側〜キッチンに向けて勾配天井にし、キッチン上は棟違いの吹き抜けにして奥行きを感じられる形に設計させて頂きました pic.twitter.com/9468DoICDV
部屋数が多いと壁やドアが増え、その分建築コストがかさみます。
また、延べ床面積が広いと坪単価がそのまま建築費に反映され、コストアップの要因になります。
- 子ども部屋を1部屋にまとめる
- リビングを広めにして廊下を少なくする
- バルコニーを省略する
| 削減項目 | 効果 |
|---|---|
| 部屋数を減らす | 壁やドアの削減、設備費用の軽減 |
| 廊下を短くする | 有効面積が増え建築コストが下がる |
| バルコニーをなくす | 防水工事や手すり費用をカット |

部屋数や延べ床面積は、家族のライフスタイルをよく考慮した上で調整すると無駄を省けます。
箇所③:後付けできるオプション
■[図解]付ければよかった…を防ごう!
— ニシ|住まいコンサル (@level_nishida) February 15, 2024
注文住宅を建てるなら一度は検討すべきオプション12選
暮らしの質が大きく変わる新築のオプション
一生住む家なら、予算の範囲内で「快適さ」を最大化しよう😉#注文住宅 pic.twitter.com/fvOYBeTEvr
後から設置できるオプションや設備は、初期費用を抑えるために保留しても問題ありません。
特に、外構やカーテンレール、照明器具などは、引き渡し後に自分で設置すればコストダウンにつながります。
- 外構工事(フェンスや植栽)
- 照明器具(ダウンライトやペンダントライト)
- カーテンレールやブラインド
- 太陽光発電パネル
後から設置可能な設備は、まず必要最低限のものを選び、入居後にじっくり検討すると無駄が減ります。

まずは優先度の低い部分からコストカットし、生活に支障が出ないよう調整しましょう。
内装のグレードや部屋数は調整しやすく、後から取り付けできる設備を後回しにするのも効果的です。
予算オーバーしたときに削るところについて、さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
注文住宅の予算オーバーでも削るべきではない4つの箇所

注文住宅で予算オーバーした場合、削減すべき箇所を慎重に選ぶ必要があります。
中でも、生活の快適性や安全性に直結する部分はコストダウンすべきではありません。

ここでは、削るべきではない4つの重要箇所を解説します。
箇所①:断熱材
基礎一体打ちで侵入経路は外側しかない。
— ふね🪬家づくり船員🧚💫〖Explicit〗 (@kntrygentleman) April 12, 2022
基礎外の防蟻断熱材(しかも高基礎)を果敢に進んできたシロアリは板金にぶつかり絶望。
それでも何とか土台に到達出来たとしてもホウ酸が待っている。
私は予算オーバーになったとしてもこういう家を建てたかったです。
#全て素人の想像です👁シナシナ https://t.co/dwyp8M3FlR
断熱材は、家全体の快適性や省エネ性能に大きく影響します。
特に、寒冷地では断熱性能が低いと冷暖房費が増加し、長期的に高コストとなります。

また、結露やカビの発生を防ぐためにも、適切な断熱材を選ぶことが重要です。
- 冷暖房効率が悪化し、光熱費が増加
- 壁内部の結露によりカビ発生
- 室内環境が悪化し、健康リスクが高まる
| 高性能断熱材 | 断熱性能 | メリット |
|---|---|---|
| ロックウール | 高 | 防音効果もあり快適性が向上 |
| ウレタンフォーム | 非常に高 | 気密性が高く、冷暖房効率が良い |
| グラスウール | 中 | コストパフォーマンスが良い |
初期費用を抑えるために断熱材を妥協すると、後々の光熱費やメンテナンス費用がかさむため、削減は避けましょう。
箇所②:セキュリティ設備に影響する箇所

安全な生活を送るためには、セキュリティ設備が欠かせません。
玄関ドアの鍵や窓ガラスを低コスト品に変更すると、防犯性が著しく低下します。
特に、ピッキングに強いディンプルキーや防犯ガラスは、住宅の防犯性能を高める重要な設備です。
- 不正侵入リスクが増加
- 空き巣被害で物的損害が発生
- 保険金が下りないケースもある
- ディンプルキーやスマートロック
- 防犯ガラスやシャッター付き窓
- 監視カメラや防犯センサー

安全性を軽視してコストを削ると、万が一の被害時に後悔するため、最低限のセキュリティ対策は確保しましょう。
箇所③:耐震装置

日本は地震が多発する国であり、住宅の耐震性能は生命を守るために欠かせません。
特に、「耐震等級3」を目指すことで、災害リスクを大幅に軽減できます。
耐震性能を落とすと、万が一の災害で家屋が倒壊するリスクが高まります。
- 大地震で家屋が倒壊する恐れ
- 地震保険の割引が適用されない
- 修復費用が莫大になる可能性
| 耐震対策 | 内容 |
|---|---|
| 耐震金物の強化 | 柱や梁の接合部を強化する |
| 制震ダンパー | 揺れを吸収し、建物の損傷を軽減 |
| 免震構造 | 建物自体を揺れから守る高性能対策 |

災害から命を守るためには、耐震性能を削らず、しっかりと確保しておきましょう。
耐震に関して詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
箇所④:水まわり等の設備

キッチンや浴室、トイレといった水まわり設備は、生活の快適性を大きく左右します。
水まわりが不便だと、毎日のストレスが増え、リフォーム費用がかさむ恐れもあります。

特に、耐久性が求められるトイレやバスルームは、標準仕様以上のグレードを選ぶと安心です。
- 水漏れや排水トラブルが発生
- 日常的な不便さがストレスに
- メンテナンスコストがかさむ
- 高耐久シンクやステンレス製キッチン
- 節水型トイレや自動洗浄機能付き
- 浴室乾燥機や自動追い焚き機能
水まわりの設備は日々の生活を快適に保つために必要不可欠です。
品質を落とすと使い勝手が悪くなり、結果的にリフォーム費用がかさむため、コスト削減は避けるべきです。
「新築で予算オーバーで払えない」に関するよくある質問5選

新築住宅を計画する際、予算オーバーで悩む方は多くいます。

ここでは、よくある疑問について解説します。
質問①:新築の予算オーバーで後悔する理由はなに?
元々第一希望は住林だったけど1000万くらい予算オーバーだったから諦めて今は後悔ないけどやっぱり隣の家とか同級生が新築建ててすみりんだったら
— nana (@oynQJJA42rXp6ZL) November 17, 2023
「いいなぁ…🤤🥹🥹」
とは一生なると思うww憧れの住林🥹
ついに新築一戸建ての契約を結んできたー!
— のい◢ ⁴⁶ (@noy_w_aym) February 12, 2024
計画し始めて2年くらい?かな
年末までには建つ予定だけど、
楽しみな反面、お金がなー笑
結局予算オーバーしたし、契約金で5年ぐらい掛けて貯めたお金も飛ぶし笑笑💸
でもまぁ後悔はない!
最高の家が建つことに期待してる🏠
新築住宅で予算オーバーして後悔する理由は、無理のない返済計画を立てられなかったことが大きな要因です。

特に注意が必要なのが負担率です。
返済負担率とは、年収に対する住宅ローン返済額の割合を指します。
一般的には20~25%以内が安心とされていますが、これを超えると家計が圧迫されやすくなります。
| 年収 | 年間返済額 | 返済負担率 |
|---|---|---|
| 400万円 | 80万円 | 20% |
| 500万円 | 125万円 | 25% |
| 600万円 | 180万円 | 30% |
返済負担率が高くなると、以下のような問題が発生しやすくなります。
- 生活費の圧迫
家計が苦しくなり、普段の支出を削る必要が出てくる - 貯蓄ができない
予期せぬ支出に対応できず、緊急時の備えが不足する - 精神的ストレス
返済が負担となり、家を持つ喜びが薄れてしまう
- 借入可能額ではなく、返済可能額を基準に計画する
- 生活費や貯蓄も含めた資金計画を立てる
- 家族構成や将来の支出を考慮して無理のない返済額を設定する
住宅ローンの審査に通っても、実際に返済を続けられるかどうかが大切です。
無理のない計画を立てることで、後悔を防ぎましょう。
質問②:新築の予算オーバーで1,000万円はありえる?
これからは色んな単価も高騰しているので、新築を建てない選択を取られる方も増えてきそうですし、無理して建てなくてもとも思います。ぬーしんさんのように、1000万円予算オーバーしても、何かを捨てたり副業頑張る決意で家を建てて、また違う何かを得れたらそこに価値がありそうですね✨
— ファンタジスタふじもと|家づくり (@fujimonchannel) April 26, 2022

はい、ありえます。
特に注文住宅では、以下の要因で予算が大幅に増加するケースがあります。
- 土地代の高騰やエリア選定ミス
- オプションや設備グレードのアップ
- 地盤改良や外構工事などの付帯工事費
- 契約後の金利上昇によるローン返済額の増加
- 設計段階で詳細見積もりを確認する
- 土地購入費と建築費のバランスを意識する
- 予備費を確保しておく
質問③:注文住宅の予算オーバーの平均はどのくらい?

注文住宅の予算オーバー額は、200~500万円程度が一般的です。
以下は、主なオーバー理由と金額の目安です。
| 理由 | 平均オーバー額 |
|---|---|
| 仕様変更やオプション追加 | 100~300万円 |
| 地盤改良費の発生 | 50~150万円 |
| 付帯工事費(外構など) | 50~100万円 |
| 設備アップグレード | 50~200万円 |
契約後の仕様変更やオプション追加が多いと、最終的に大きく予算を超えるケースが目立ちます。

初期の打ち合わせ段階で、しっかりと必要な費用を把握しておくことが重要です。
質問④:注文住宅の予算オーバーで購入を諦めた人はいる?
新築時に予算オーバーで諦めたウッドデッキをDIY。木材はすべて貰い物。コストは1万円ほど。雨ばっかで塗料塗るのに苦労した。窓サッシすれすれにできて満足🙌#DIY pic.twitter.com/nEjkVgwGte
— じんろく 🍀 キャンプ (@Jinroku1001m) August 16, 2021
ええーいいなー カウンターキッチンで1階コンビニでーって新築の賃貸マンションを家賃が少し予算オーバーしてて諦めたのよねー 今んトコでも満足はしてるけどもー
— 八重樫 剛 (@tkc_exp) January 29, 2011

はい、実際に購入を断念したケースもあります。
特に、以下のようなケースで購入を諦めることが多いです。
- ローン審査が通らなかった
- 仕様変更で総額が予算を大幅に超えた
- 家族の意見がまとまらず決断できなかった
- 金利上昇で返済計画が崩れた
住宅会社と早めに相談し、コストダウンの方法を共有することで、購入断念を防げる場合もあります。
無理に進めず、一度立ち止まって再検討することも必要です。
質問⑤:注文住宅で予算オーバーしたら解約はできる?
移住計画
— 【公式】🐺ゴルちゃんTV🐺 (@GORU2020) February 4, 2024
現地に内見しに行って来ました!
250坪はめちゃ広‼️
しかし、瓦は剥がれ穴が空き雨漏りが激しく
白アリにも食われ家自体がかなり傾いて居ます…
こりゃぁ修理するより新しく建てる方が早そう
しかし、新築となるとかなり予算オーバー…
どうしよ😨?
ちと考えてみます pic.twitter.com/H0UQTBDuFt
契約内容や進捗状況によって解約は可能ですが、解約には違約金が発生するケースがほとんどです。
- 契約金(着手金)の返金不可
- 工事の進行状況に応じた違約金
- 設計費や工事費の一部負担
- 契約書に記載された「解約条項」をチェックする
- 住宅会社に解約時の費用を確認する
- 弁護士や専門家に相談してリスクを確認する
契約前に解約条件をしっかり確認しておくことが大切です。

解約を考えた時点で、できるだけ早く住宅会社と相談しましょう。
解約を考えた時点で、できるだけ早く住宅会社と相談しましょう。
新築を建てるときの不安の解消法については、こちらの記事をご覧ください。
まとめ:新築で予算オーバーしないために、入念な資金計画を立てましょう

- 新築住宅で予算オーバーしないための資金計画
- 削るべき箇所と削らない箇所の見極め
- 柔軟に対応できる住宅会社の選定
新築住宅の予算オーバーは、計画段階での見落としや、契約後の変更が原因となりがちです。
無理のない返済額を把握し、借入可能額ではなく返済可能額を基準に計画を立てましょう。

また、コストダウンできる箇所と妥協すべきでない部分を明確にし、柔軟に対応することが大切です。
入念な資金計画を心がけ、安心して新築住宅を手に入れましょう。