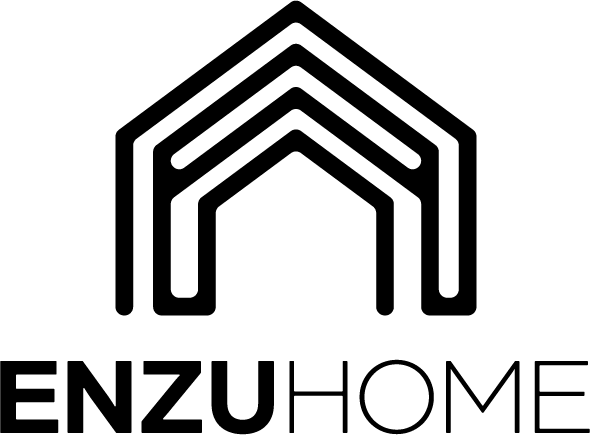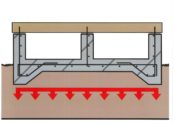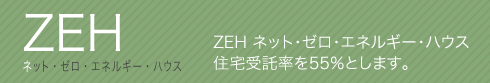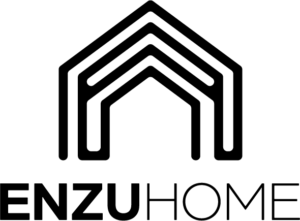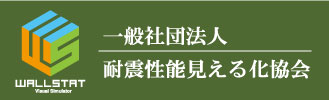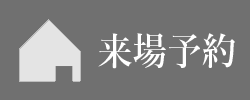諸費用・諸経費とは!!住宅取得の際のまとめ

皆さん~この項目忘れてると最後に焦りますよ~!それは、家づくりにおいて目を背けることのできない諸費用。一口に諸費用と言ってもかなりの項目と費用が嵩みます。だけど、この項目から目を背けると後々大変な目に遭いますので、そうなる前に心づもりしておく事で対策が打てたりします。
◆今回はこんな方の為に書いています。
⇒これから住宅を建てる方全般
⇒諸費用って何が該当するの?という方
◆今回の記事を読むとこんな事がわかります。
⇒各諸費用の項目と費用感
⇒見落としがちな諸費用項目
◆こんな方は読まない方がいい
⇒時間のない方
諸費用:仲介手数料
この記事のもくじ
- 1 諸費用:仲介手数料
- 2 諸費用:上下水道市納金
- 3 諸費用:固定資産税精算金
- 4 諸費用:不動産取得税
- 5 諸費用:住宅ローン保証料
- 6 諸費用:住宅ローン事務手数料
- 7 諸費用:団体信用生命保険
- 8 諸費用:印紙代
- 9 諸費用:つなぎ事務手数料・経費
- 10 諸費用:設計費
- 11 諸費用:地盤改良費
- 12 諸費用:土地所有権移転登記
- 13 諸費用:表示・保存・設定登記
- 14 諸費用:火災保険
- 15 諸費用:引越し費用
- 16 諸費用:仮すまい費用
- 17 諸費用:確定測量費用
- 18 諸費用:分筆費用
- 19 諸費用:解体費用
- 20 諸費用:浄化槽維持管理費
- 21 諸費用:上棟時・入居時挨拶等
- 22 諸費用:家具代
- 23 諸費用:インテリア関連
- 24 諸費用:地鎮祭
- 25 諸費用:諸証明書他
- 26 諸費用:まとめ

土地を購入する際、不動産屋さんが仲介に入ると、(不動産成約価格*3%+60,000)+消費税が一般的ですが、厳密にいうとこの計算式は不動産の成約価格が400万円超の場合です。因みに200万~400万円以下は(不動産成約価格*4%+20,000)+消費税。200万円以下の場合は(不動産成約価格*5%)+消費税。
これは、不動産屋さんがこのブログ見たら【余計なこと言うな~】とお叱りを受けるかもしれませんが、受け取れる報酬の上限です。だからと言って仲介手数料を値切っても良いと言う事ではありません。安心して取引できる事への対価と考えると良いかもしれませんね。
諸費用:上下水道市納金
これ、よく勘違いされる項目なんですが、全面道路から建築敷地内へ水道の本管を引き込む工事ではなくて、道路から本館を敷地内に引き込んだところに水道メーターが付きますよね?その水道メーターの権利金?みたいなもので、市やその行政エリア内の水利権?を持った団体へ支払う費用です。
これは各行政によって費用感はバラバラで、安いと数万円、高いと十万円単位で費用が必要になります。この費用は土地を買う時には必ず不動産屋さんから説明を受ける【重要事項説明書】に記載のある項目で、サラッと聞いていると、、、まあまあ後でビックリします!
そうならない為にも、しっかり重要事項説明書の説明を聞く事やもしくはご自身で、その行政に確認をすると確実です。市役所などに水道課が入っている場合はまだ良いですが、別の場所に建物がある場合がありますので事前に市役所の【水道の市納金について】と問合せをすると無駄足を踏まずに確認できると思いますので、少しだけ注意が必要です。
まれにこの市納金が【不要】の場合もあります。その場合とは、購入した土地にすでに既設管として残っている場合。その場合はその水道メーターの権利を移転し名義を変更すればOKです。
少し話はそれますが、既存建物がある状態で不動産売買をする場合、この水道メーターの権利を土地代金とは別に請求する不動産業者さんも有ります。これは別にセコイ訳ではなく、その業者(売主さん)の意向次第ですので、サラッと確認したほうがいいかもですね。
諸費用:固定資産税精算金

固定資産税清算金は 土地を契約し、土地の残代金を支払う際(所有権移転時)にその日を境にして決済日までを売り主さん。決済日からを買主さんが負担する事になります。(地域性はあるかもしれませんが、愛知県はこんな感じです)それと、固定資産税の起算日も地域性があるようです。愛知県では起算日を4月1日としています。仮に決済日が5月1日だとすると売り主さん負担日数は4月1日~4月30日までの30日分・買主さんは5月1日から3月31日までの335日分となります。
諸費用:不動産取得税
土地や建物を買ったときにかかる税金で、土地購入や新居に引っ越してから脅迫状の様に納税通知書が送られてきます!ややこしそうだし、放っておこう!なんて考えは捨ててくださいね。逃れることはできませんので(笑)ただし、ある要件を満たせば軽減されるので納税通知書が届いたからと言って焦る必要はありません!
不動産取得税の税額は、「課税標準額×税率」で計算されます。課税標準額と聞くと難しい、、、もうこの時点で拒否反応が出る人も多いと思いますが、簡単にいうと、その不動産の価格のこと。とはいえ、実際に売買したときの時価ではなく、固定資産税評価額と呼ばれる公的な価格が使われます。
この評価額は時価よりも低い場合が多く、土地の場合は時価の7割程度、建物の場合は5~6割程度が目安と言われています。
税率は原則4%ですが、土地と住宅については2021年3月31日の取得までは3%に引き下げられています。土地か住宅であればOKです。
また宅地や宅地と同じ扱いを受ける土地に限っては同じく2021年3月31日まで、評価額の2分の1が課税標準額となっている。
【原則】
宅地……×4%
住宅……×4%
【軽減措置】
宅地……評価額×1/2×3%
住宅……評価額×3%
※軽減措置は、2021年3月31日まで
諸費用:住宅ローン保証料
住宅ローンを利用する際に必要となる場合がある諸費用です。【住宅ローンの返済が出来なくなった時】に保証会社に代わりに返済してもらうために結ぶ 保証契約費用みたいなものです。
万一返済不能となった場合にはこの保証会社があなたの代わりに 金融機関に一括返済してもらえます。ここで勘違いしていけないのが 【借金がチャラになるわけではない】という事です。
住宅ローンは あなた(債務者)と金融機関だけの契約ではなくて 保証会社も関係しています。こちらの図です。
保証料の目安は 100万円あたり20,000円程度です。中には15,000円程度の場合もあったりします。とてもとてもいやらし~い書き方ですが、金融機関的に言うと【属性】【スコアリング】などによって、人によって変わります。貸し倒れリスクの少ない場合はこの保証料も低額になる場合が多い気がします。
また、保証料がいらないケースもあります。それは支店長決済プロパーです。金融機関的に言うと【属性】【スコアリング】共に良い方はプロパーでいけるかもしれません。ちなみに【属性】【スコアリング】に関係する項目は
・勤務先
・年収
・預貯金額(自己資金)
・勤続年数
・資産背景等
諸費用:住宅ローン事務手数料
融資を受けるためにいくつのローン商品を申し込むかでも変わってきますが、分譲住宅やマンションの場合は 1つのローンで良いですが、土地購入その後建物資金が必要になるという場合には土地ローンと建物ローンの2つのローンを借りることになります。ですので土地購入→建物建築という場合は事務手数料は 分譲住宅やマンションに比べ倍必要となります。これも各金融機関によって事務手数料の金額はバラバラで、30,000円のところもあれば100,000円のところもあります。
各金融機関のパンフレットを見てみてくださいね。
但し、金融商品(住宅ローン)で 事務手数料無料とか 保証料なしとか 目にする機会があるかもしれませんが、そこだけに踊らされずに、その他の店頭金利や固定期間選択時には【固定期間満了後の店頭金利からの引き下げ幅】の確認・および他行との比較も忘れずに!
諸費用:団体信用生命保険
命がけで住宅を買うと言われる所以はこれにあります。万一債務者(住宅ローンを借りた人)が死亡した場合は、住宅ローン返済免除となります。免除という言い方が良いかですが、、、債務者がなくなった→借りたのはあんたの旦那さんやから奥さんが払ってください。なんてことはありません。
たまに笑い話で、住宅ローンを借りるまでは旦那さんに優しくて、新居完成したら旦那さんに少しだけ冷たくなったとか、、、(笑)まあ、それは気のせいだと思います。
ここで注意が必要なのが、団体信用生命保険に誰もが入れる訳ではない事です。
団体信用生命保険申し込み時点より以前(3か月程度)に
・入院および通院があった方(病名や症状による)
・過去3年以内に 記載される病気になった方(これ数が多くて割愛させていただきます)
その他細々とありますが、申し込み時にはよく読んで問診票?告知書?のご記入を!
万一ここで 【不実告知】=嘘 なんてついたら万一の場合 とんでもないことになります。仮に何かの病気を患っている・患った事があるなどの場合でも正直に書いて保険会社の回答を待ちましょう。
ここで少し安心材料を
各金融機関ごとに 保険引き受け会社が違います。例えば
〇〇銀行の保険会社はAA保険
□□信金の保険会社はBB生命
△△組合の保険会社はCC社
だとした場合、それぞれの保険会社で返ってくる返答に違いがあります。
ですので〇〇銀行のAA保険で良くない返答が来たとしても、諦めずに□□信金のBB生命・△△組合の保険会社はCC社に申し込みしてみる等が考えられます。
諸費用:印紙代
これ簡単に言うと税金、、、いろんな所で実は課税されてます。。。
まあ、そんな事言っても話が進まないので納税は仕方なしとして。どんな場合に印紙代がかかるかというと。
・金銭消費貸借契約時20,200円*回数分(お金を借りる契約をした時)
・土地売買契約時 10,000円(売買代金による)
・建物請負契約時 10,000円(契約金額による)
(弊社の場合これ位が一般的です)
印紙税一覧はこちらです。
(国税庁より)
他には 登録免許税などもあります。
諸費用:つなぎ事務手数料・経費
これは個人的に一番もったいない費用のような気がします。
住宅ローンの融資のタイミングにもいろいろあり、確認申請済証があればそれをもって建物代金を融資してくれる金融機関もありますし、そうでない金融機関もあります。
この、建築確認済証をもって建物代金を融資してくれることを【設定前融資】や【着工時融資】などと言ったりします。要するに 完成時に住宅ローンを融資(実行)するわけではなく、建築が始まる前に建物代金分の融資をしてくれるという融資のタイミングです。
この設定前融資や着工時融資の場合のメリットは 建築屋さん(工務店やHM)に請負契約通りに支払いができるという事。そうでないと請負契約の支払時期と金額に違反することとなります。逆にデメリットは融資を実行した翌月の支払約定日(お客様が引き落とし指定した日)に住宅ローンの支払いがスタートします。
もちろんこの支払は 建築工事中も 現在の家賃と重複しますので、、、それ つらい、、、という場合に つなぎ融資を利用する場合があります。
この設定前融資や着工時融資は建築屋さんの金融機関からの評価評定により可能かどうかが分かれます。ですので設定前融資や着工前融資をしてもらえる建築屋さんか否かで建てようとしている建築屋さんの金融機関からの信頼度がある程度透けて見える訳です。
さてさて、ここから つなぎ融資についてです!前置きが長かったですね、、、<(_ _)>
つなぎ融資は 簡単に言うと 住宅ローンの毎月の返済はしなくて良い。これだけ聞くと【ぜったい つなぎ融資の方が良い!】となりそうですよね?
しかし!
そうは問屋はおろしません。 通常は建物代金は完成時に融資実行します。その間建築屋さんにお支払いするお金ありませんよね?それ請負契約違反になりませんか?ではウチがお貸ししましょうか?その代わり利息だけはくださいね。その利息は3.475%位ですから(金融機関に要確認)。 ね?毎月の支払いに比べればお安いでしょ?的なトークで金融機関はつながせたがる?そんな事もないかな(笑)
ではここで少々つなぎ融資の計算をしてみましょう。
建物請負契約金額3000万円として(例)
着工時1000万円
上棟時1000万円
引渡時1000万円とした場合(ちょっとざっくりし過ぎたかな?)
そして工事期間が着工から仮に5か月かかるとして
着工時の支払から5か月=150日(ひと月を30日としました)計算が簡単だから
上棟時の支払から3か月=90日(ひと月を30日としました)計算が簡単だから
そして引渡時に最終的に建物代金分の融資スタートとします。
その場合のつなぎ利息は
着工時からの分で1000万*3.475%*150/365=142,068円
上棟時からの分で1000万*3.475%*90/365=85,685円
つなぎ利息合計=227,753円
ん???227,753円なら まあ仕方ないか、、、請負契約違反になって工事が止まったりしてもあれだしな~と考えるのはちょっと早いです!
仮に3000万円の融資を実行した場合
毎月の返済は変動金利0.5%と仮定
借入期間35年とした場合
毎月支払い金額=77,875円*実行後支払い期間4か月=311,500円
やっぱり311,500円は大きいし、毎月7万円の家賃と重複する支払いは厳しい、、、
まだまだ、ちょっと待って~ お金を支払う行為に違いはありませんが、その先のお金の性格というかどこに消えていくかに注目してほしい!
つなぎ融資は毎月の重複する金額は少額だけど、これは金融機関に対する利息。あくまでも利息。貸してくれてありがとう♪代です。
一方融資実行の毎月7万円の支払いは 自身の借入に対する返済の為、当然元金に充当されていきます(一部ですが)。要するに自分が借りたものに対しての支払という事です。
つなぎ融資利息を払ったところで 自身の借入額は減っていきません! で、あれば少々頑張って 返済スタートした方が良くない?その分最初に資金計画をして自己資金をコントロールした方が長い目で見たら損はない!という事です。
ですので、つなぎ融資対応しかできない金融機関はお勧めしないという事です~♪
諸費用:設計費
こちらの費用は 住宅を建てる為の設計図を書いてもらうための費用です。
へ~お金かかるんだ~。
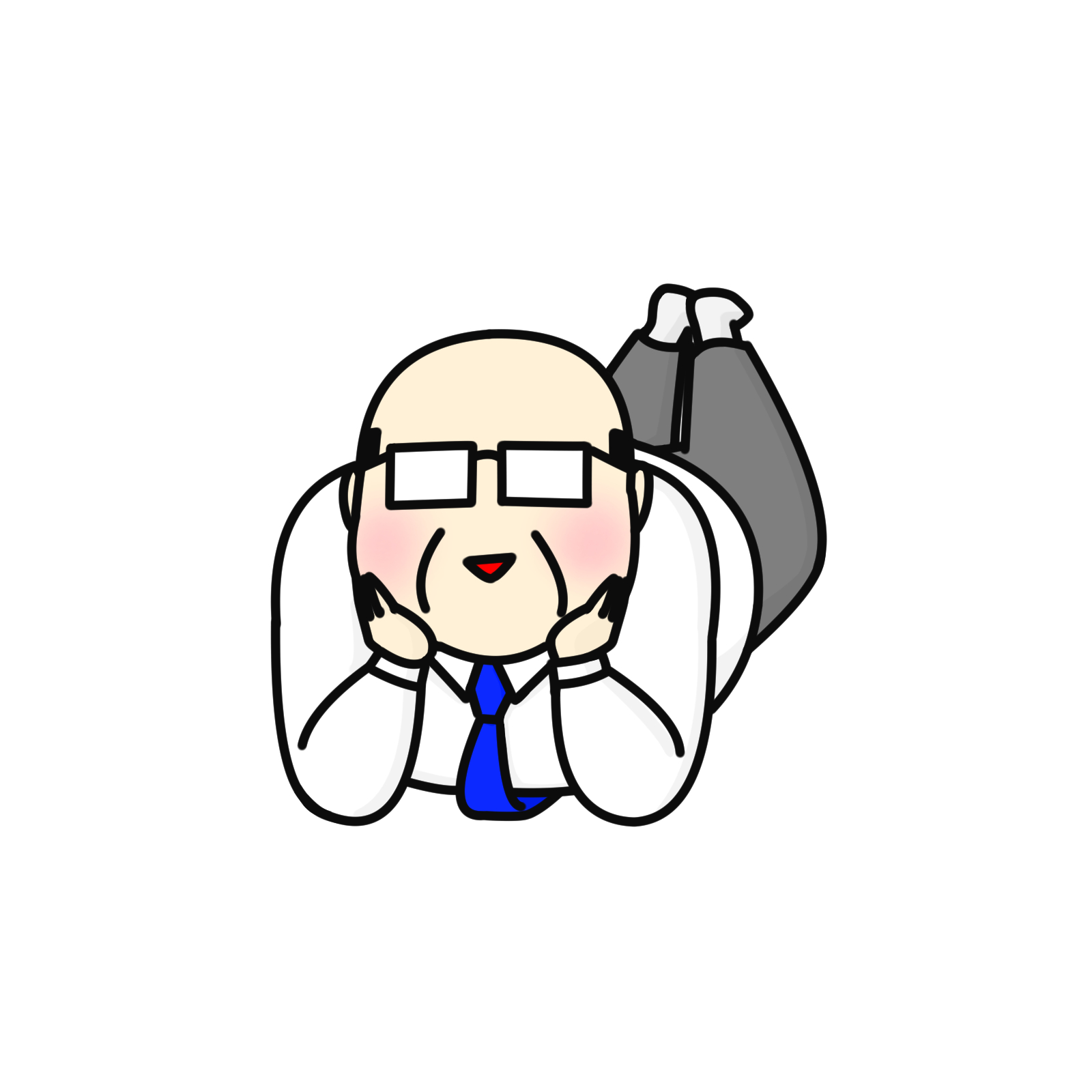 とーさん
とーさん
そうです。設計図を書いてもらうにはお金が掛かります。では誰に書いてもらうのか?それは、建築士の免許をもった方が書くのが一般的です。
たまにハウスメーカーさんや工務店さんの営業さんが書く場合もありますが、営業さんが書いた図面は【絵】でしかないんです。。。結局は確認申請業務を提出できるのは設計士さんです。(有資格者)
有資格者とは国家資格合格者です。国家資格合格するにはかなりの勉強をされたはず。その方に書いていただく図面は価値のあるものです。ましてやお客さん自身が書いた図面では当然住宅が建つはずもなく、その図面を実際建つようにアドバイス(構造面・法令面・温熱面・意匠面等々)をするのも設計さんの仕事かもしれません。
また、お客様の【どう住みたいか?】【どんな暮らしがしたいのか】をヒアリングしてそれを形にするのが設計士さんの腕の見せ所でもあります。
設計費用の目安はどこまでの設計を依頼するかで大きく変わりますので、設計者さんにお尋ねいただくと良いかと思います。数十万円から建物規模によっては数百万円なんてこともあります。
諸費用:地盤改良費
この項目って意外と見落としがち、、、というか悪意?のある会社だと【別途工事】としてあるだけ。。。確かに別途工事ではありますが、建物の規模などが決まった段階で調査をして改良工事の有無や、必要だという判定が出た場合の見積を先に取っておくほうが後でこうなりません↓
ぎゃ~!!!聞いてない!そんなお金今さらどうやって。。。
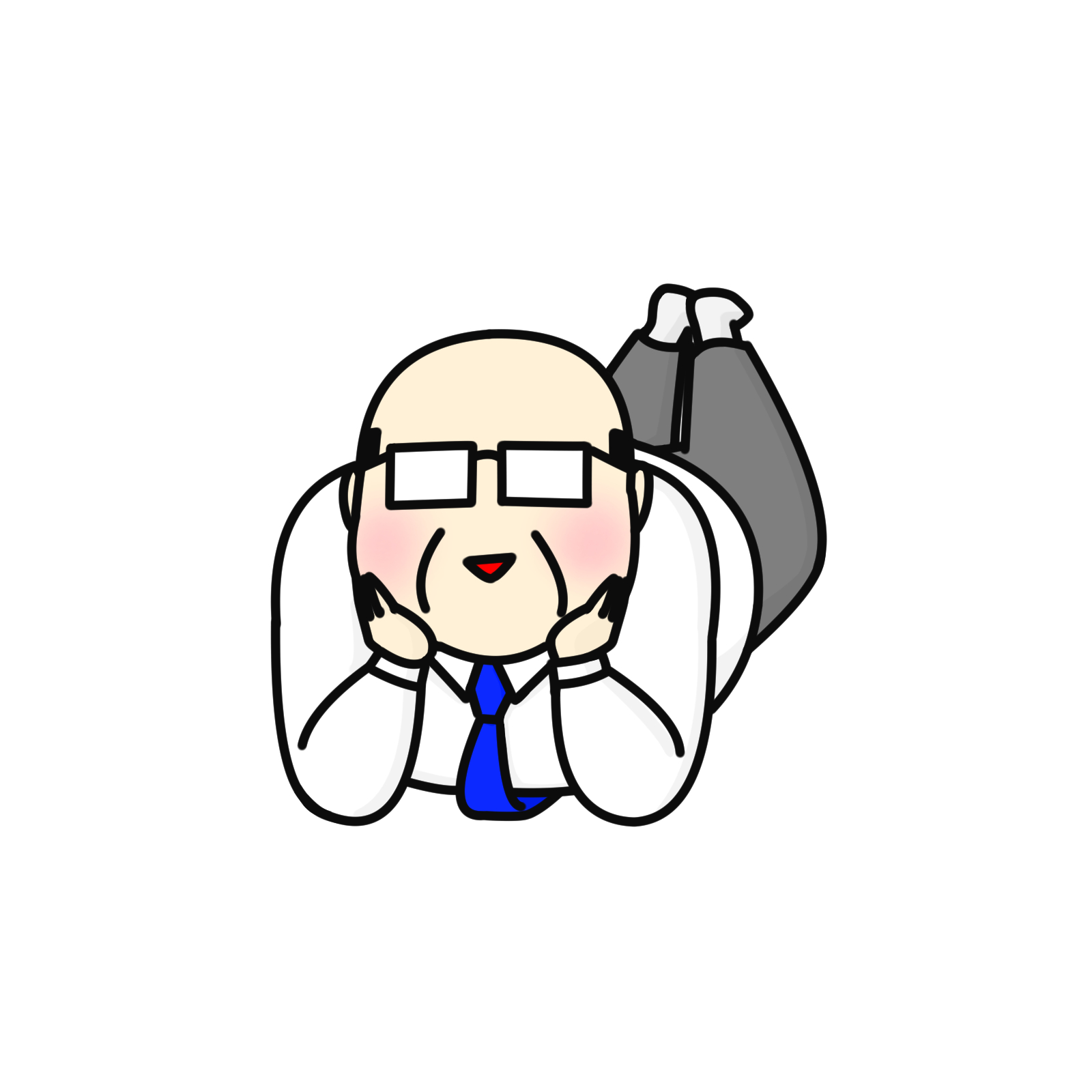 とーさん
とーさん
あんた寝ずにバイトするしかないな。。。
 かーさん
かーさん
こうなってしまっては楽しいはずの家づくりが楽しくなくなります。
なるべく早めの地盤調査をして(建築規模・配置などが決まった時点)地盤改良費の金額を把握した方がよさそうですね!
上記の方法が地盤改良工事費を把握する方法ですが、もっと手前である程度目星をつける方法もあります。それは、今昔マップや地理院地図で昔その土地がなんだったのか?どういう地形だったのか?をみて見るのも有効な手段です。
数十年前はここは 田んぼだった=地盤改良工事は必要そうだな。
もう一つは、近隣地盤データを見て推測するという方法もあります。この近隣地盤データは建築する会社さんを通じて地盤改良工事会社に問い合わせしてもらうといいと思います。
諸費用:土地所有権移転登記
不動産価格によりますがこちらを参考にしていただくと良いかな?
諸費用:表示・保存・設定登記
土地を不動産屋さんで購入する場合見落としがちなのがこの登記費用。表示・保存・設定登記
表示登記・保存登記とは人間でいう所の【出生・命名】の家バージョン。設定登記とは新しく生まれた家にお金を借りた事の証を書き記す(あくまで謄本に)という作業です。金融機関からすると、返済不能などになった場合 回収不能にならないための措置ですね。
おおよその費用ね目安は建物価格や借入額によって代わりますので担当者さんにご確認ください。
諸費用:火災保険

引渡し後、無保険で家が火災になってさあどうしよう、、、もう一軒同じの建てるか!
なんて事にはならないと思います。その最悪な状況にならないためにも 火災保険は入っておいた方が良いです。ではこの火災保険ですが、建物価格や補償内容によっても随分と変わります。もっと言うと地域性によっても変わります。火災保険自体はそんなに高額にはなりませんが、この時世です。。。地震保険が結構高い?(そんなことないか、、)高く感じるのは5年MAX(一回の契約で)ほかに高い?と感じるのは家財保険ですね。
保険なので補償内容が充実しているに越したことはないですが【あれもこれも】だと、、、目が飛び出るくらいになるので、内容をよく吟味してみてはいかがかな?と思います。
諸費用:引越し費用
有名会社から、ガレージブランドではないですが聞いた事の無いような会社さんまであります。どこがいいかは正直わかりません。営業の人が良くても実際作用する人が【雑】だったら何の意味もない訳で。。。大手さんはその辺の教育がしっかりされているのか?それも良く分かっていません。
何故ならオガタは引っ越しを3回ほどしましたが、外れにあたったことがないからです。小さな有名ではない会社さんですが特に不満に思う事はなく無事にできました。3回の全部の引っ越しを頼んでいるから?というのも有るのかもしれません。
引っ越しってなると なかなか断捨離できずに 奥から出てきたモノを見て 【いるかもしれない】 という思いにふけると 引っ越しの準備の荷造りのはずが、ただの【荷物の移動】をしているだけになってしまいがち。。。(笑)
半年から一年ず~っと開封していないダンボールや動かしていないものでしたらそれは思い切って捨ててみてもいいのでは?と思います。
避けたい引っ越しの次期は 3月と4月 この時期は特に高い!需要があるから。。。お客さんの話だとその時期になると通常時の2倍位は当たり前で、3倍ほどの価格提示をされた、、、なんてお話も聞きます。
こそこそ話ですが、知り合いの引っ越し屋さんは3月は繁忙期でどうしても人手が足りず、断りたいから通常時の見積もり金額よりも3倍の見積額提示をしたらそれでも依頼された、、、と複雑そうな表情で小縣に話してきた記憶があります。
諸費用:仮すまい費用

この項目は全ての方にかかるわけではありませんが、現所有地に建て替えの場合やリフォームなどの時にかかってきます。軽く仮住まい費用と言ってもですね、月の家賃が仮に8万円場合。仮住まい期間が6ヶ月+敷金礼金がそれぞれ1ヶ月づつだったとすると合計で64万円の出費となります。
これに引っ越し費用も加算されますのでまあまあの出費間違いなしです。
もう一つ老婆心ながら、、、今のお宅から仮住まいの部屋に引っ越しとした場合、少しの期間だし今より少し小さなアパートを選んだとすると、荷物の行き場がない、、、レンタルコンテナを借りなければ、、、ということも考えられますので少しの期間とはいえど出費は大きくお客さんにダメージを与えることになります。
諸費用:確定測量費用
確定測量とは所有地やこれから購入する土地を分筆する場合にしなくてはならないと思ってもいいかな?細かい話。
市街化区域で机上分筆がOKでしたら確定測量をしなくても良いのですが、市街化調整区域の土地で大きな土地の中にもう一件建てようとすると、分筆しないといけなくなります。この確定測量を行った日がそんなに昔じゃないのなら、その時の座標が使えるので良いのですが、古いと当時の測量精度がよくないので確定測量をしてある土地でも再度【確定測量】をしなくなるケースもあります。その費用は隣地の方の人数などにもよりますがおおよその費用感は35万円〜という感じでしょうか。
諸費用:分筆費用
確定測量も終わり(以前の確定測量日が直近であったり)さあ、分筆といった段階では、どこをどのような範囲を分けるのか?をしっかり決めて分筆の手続きとなります。
この時大切なのが、残る土地と新しく生まれる土地の関係です。大きな土地から新しく生まれる土地があるわけですが、この時残る土地の上に建つ建物が建ぺい率オーバーにならないようにしなければなりません。
建ぺい率とは?こちらをご参照ください。
仮に建ぺい率オーバーになっても直接の罰則はありませんが、将来その土地・建物を売却する際に不利になります。そうなってからでは遅いのでくれぐれも分筆の際はその点をお気をつけ頂く事と、越境の有無の確認は重要な項目となります。
分筆費用の相場は 折点の数にもよりますが、単純なもので10万円〜15万円ほどです。
似たような項目で容積率というものもあります。ご参考までに。
諸費用:解体費用
これも規模と内容によりますので一概に幾らとは言いにくいのですが、木造住宅の場合50万〜100万円程度見ておけばほぼほぼ解体できる感じかと思います。いや、もうちょっとかかるかな?
そこに残地物の撤去やリサイクル費用などがかかる物品がどれだけあるか?植栽は?隣地ブロックは?残土は?地下埋設物の有無などなどの費用が加算されていくイメージです。
解体屋さんも得手不得手がありますので、A社は高いB社はお値打ちという事がありますが、解体屋さんって横着なイメージをお持ちかもしれませんが今の時代はすごく丁寧な解体屋さんも増えてきています。しっかりと近隣への挨拶周りなども丁寧に行ってくれるところが増えています。
諸費用:浄化槽維持管理費
下水供給エリアでは不要なこの費用。これは何かというと、浄化槽を維持管理するための委託費用のようなもの。これは確か、所有者は定期的に法定点検をしなければいけなかったはず。。。なので、【点検を受けないよ〜】なんて事はできないはずです。万一、点検を受けずに故障
なんて事になったら、、、浄化槽入れ替え、、、目も当てられません、、、この法定点検以外にも年に一度くらいは汲み取り費用もかかります。これも放っておくと浄化槽の中が満タンになり、正常な機能を果たせなくなったりして、異臭を放ち出したりする恐れもあります。
こういう費用は節約?ケチる?と後で大きなしっぺ返しが来る場合が多いので、真面目に普通にやる事がいいのかなと思います。
諸費用:上棟時・入居時挨拶等
まあ、これの上棟時・入居時挨拶などでかかる費用を、諸経費と呼ぶかどうかですが、住み出す前にかかる費用として考えれば計上しておいてもいいのかな?と思います。
まずは、上棟時ですが、上棟式をなさるのであればその神主さんにお支払いする費用が3〜5万円程度?かかります。それにお供えやお神酒など、雑費として諸々かかります。また、上棟式に誰が来るかと規模によりますが、大工さんなどがお見えになる場合は寸志なども気になりますよね?
次に入居時の挨拶などに持っていく手土産など、こちらは1000円〜3000円程度?の物を近隣の方達に挨拶しながら廻ります。なのでその廻る件数によります。それ以外には地元の会長さんなども入るかと思います。
諸費用:家具代
これは諸費用とは言わないかもしれませんが、新築に伴って購入する家具って必ずといっていいほどありますよね?というか、出てきます(笑)
家具って簡単にいっても、ピンからキリまでありますので、意中の家具があるのでしたら前もって諸費用計上しておいた方がいいかもしれません。
新築住宅と植栽関連にお金を注ぎ込みすぎて、、、意中の家具が買えなかった、、、では寂しいですからね。家具は個人的には完成形が見えてから色合わせをした方が良いと思ってますので、現場の内装が完成した段階で内部を見せてもらってから家具屋さん巡りをする方が良いのかな?と思います。欲しい気持ちが先走って内装の色や雰囲気の確認をする前に購入して、搬入したらイメージがちょっと、、、とか色がきついな~とかという事が防げれます。
諸費用:インテリア関連
カーテンの部類。カーテンもピンからキリまで、、、せめて一階のお客様の目につくような箇所は以前の使い回しでは、、、ちょっと頑張るか!となります。(多分)
そうなると2〜3万とは行きません。となると2〜3万ではなく 0 を1つつけておくと良いかもしれませんね。ま
また、カーテンレールをつける場合はエアコン設置後の方が良いと思います。先にカーテンレールをつけてしまうとエアコンの設置個所によってはエアコンが取り付けれないという事にもなりかねませんので。
諸費用:地鎮祭
俺は神なんて信じねーぞ!今までも特に、これからもそんな事は関係ないぜ〜!という方はあまりいないと思います。
なんだかんだと、そういう方もきっと、初詣に行っているはず(笑)
であれば、新築の際には着工前に、その土地の神様に挨拶するという意味合いで地鎮祭はしておいた方が良いのではないかな?と思います。
地鎮祭の相場は、宗派や規模にもよりますが、おおよそ3〜10万円の間で収まると思います。
諸費用:諸証明書他
住民票・印鑑証明書・所得証明書・戸籍等(場合による)を取得する必要が出てきます。
また、家づくりの終盤では、新住所の印鑑証明書・新住所の住民票なども必要になります。数千円かもしれませんが住み出すまでにかかる費用としては計上しておいてもいいのかな?と思います。
おおよそ数千円で済みますね。ですのであえて新居に住むまでの【諸経費・諸費用】として計上しなくても、、、と思うかもしれませんが、住みだすまでにかかる費用として計上しておくと良いと思います。数千円とは言え痛いときは痛いんです。。。
諸費用:まとめ
ここまで、ずらずら〜と 住み出すまでにかかる費用=諸費用を書き記してみました!まだまだひょっとしたら漏れはあるかもしれませんが、ほぼこれ位かと思います。
数千円のものから中には数十万円・数百万円の項目もあります。
決して建築会社さんの提示する【建物本体価格】だけで家が建つなんてお考えにならないでくださいね!
皆さんが知りたいのは【建物本体価格】ではないはずです。住み出すまでの総額を知らないと楽しいはずの家づくりが途中から苦痛・金銭的/精神的にも地獄に陥ります。
住み出すまでの費用は【本体価格+付帯工事+諸費用】です。ぜひこの記事の中にある項目を参考にしてみて下さい。記事内のそれぞれの金額はあくまでも目安です。それぞれの土地・建物の状況によっては金額の増減は当然ありますので、その点もご理解いただいた上でよろしくお願いいたします!